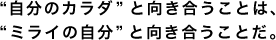患者数が年々増加傾向の子宮がん
 日本人の2人に1人がかかり、3人に1人が死亡すると言われているがんは、医療技術の進化により早期発見が可能になってきている。がんの検査方法と治療法シリーズ第18回は、50〜60歳代の女性がかかる確率が高く、2012年の罹患数第5位の子宮がんについて紹介する。
日本人の2人に1人がかかり、3人に1人が死亡すると言われているがんは、医療技術の進化により早期発見が可能になってきている。がんの検査方法と治療法シリーズ第18回は、50〜60歳代の女性がかかる確率が高く、2012年の罹患数第5位の子宮がんについて紹介する。
子宮は、子宮体部と子宮頸部によって構成されている臓器で、受精卵の着床や胎児の発育の場となるスペースといえる。そこに生じる悪性腫瘍を子宮がんといい。部位によって子宮体がんと子宮頸がんの2つに大きく分けることができる。ここでは、子宮の奥に位置する子宮体部にできる子宮体がんの検査法や治療法について解説する。
直腸診と子宮鏡検査
子宮体がんでは、まず何より病理検査が優先される。綿棒などで子宮内膜の細胞を擦り取り、顕微鏡で観察する子宮内膜細胞診だ。細胞ひとつひとつの状態がよくわかるため、がんの有無だけでなく、がんの種類まで推測することが可能である。細胞診でがんが疑わしい場合、組織診を行う。その際、子宮の中をファイバースコープという特殊なカメラで観察する子宮鏡下に組織を採取することもある。
さらに、経膣超音波検査を行い、子宮内膜の厚みを調べる検査もある。子宮体がんになると、子宮内膜の厚みが増すことから、それを確認するのだ。だが、閉経前では判断が難しく、また初期のがんは見逃されることがあるため、検診の方法としては有用と言えるだろう。
これらの検査で子宮体がんの存在が確認された場合、CTやMRIなどの画像検査によって、がんの広がりや転移などを調べていく。
子宮体がんの治療法
子宮体がんの治療では、病変部を外科処置によって取り除く、つまり手術が基本となる。ステージⅠ~Ⅱ期であれば子宮の全摘出に加え、卵巣や卵管といった左右の付属器も摘出するケースも珍しくはない。また、転移を避けるため、必要であれば所属リンパ節の切除も行う。ステージⅢ~Ⅳになると外科療法ではなく、化学療法や放射線療法で対応するケースが多い。

マーソ株式会社 顧問
虎の門病院、国立がんセンターにて造血器悪性腫瘍の臨床および研究に従事。2005年より東京大学医科学研究所探索医療ヒューマンネットワークシステム(現・先端医療社会コミュニケーションシステム)を主宰し医療ガバナンスを研究。 2016年より特定非営利活動法人・医療ガバナンス研究所理事長。

2015年滋賀医科大学医学部医学科卒業。ときわ会常磐病院(福島県いわき市)・ナビタスクリニック(立川・新宿)内科医、特定非営利活動法人医療ガバナンス研究所研究員、東京大学大学院医学系研究科博士課程在学中、ロート製薬健康推進アドバイザー。著書に『貧血大国・日本』(光文社新書)