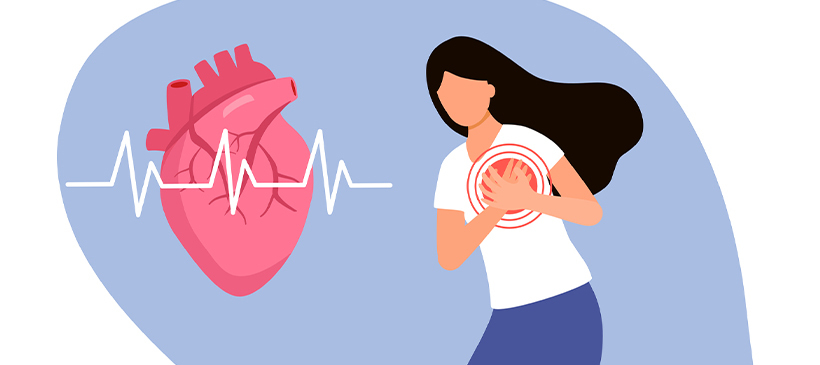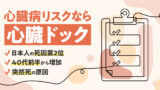心筋梗塞は、命の危険につながる重大な病気です。心筋梗塞の前兆に気づき、早急に適切な治療を行うことで、死亡のリスクや後遺症である心不全のリスクを軽減できます。本記事では、心筋梗塞の前兆や初期症状のほか、心筋梗塞になりやすい人の特徴や予防法についても詳しく解説します。
★こんな人に読んでほしい!
・30代以上の方
・高血圧、糖尿病、脂質異常症など、生活習慣病を指摘されたことがある方
・上半身に違和感があり、心筋梗塞の可能性を知りたい方
★この記事のポイント
・心筋梗塞は治療が遅れると死亡や心不全のリスクが高まるため、早期の治療開始が大切
・心筋梗塞の前兆は、締めつけるような胸の痛み、肩や腕の痛み、吐き気、冷や汗、息切れなど
・高齢者や糖尿病の方は、心筋梗塞による胸の痛みを感じにくいことがあるため注意が必要
・心筋梗塞を疑ったら、迷わず救急車を要請しよう
・心筋梗塞の予防は、健康的な食生活や定期的な心臓ドックの受診がすすめられる
心筋梗塞とは?
心筋梗塞は、突然命を失うこともある危険な病気
心筋梗塞とは、心臓に血液を運ぶ冠動脈が完全に詰まり、血液が心筋(心臓を動かす筋肉)まで行き届かなくなった状態を指します*1。血液が行き届かなくなった部分は壊死し、元に戻ることはありません。心筋が壊死した範囲が広いほど、心臓のポンプ機能は低下します。全身に十分な血液が送り出せなくなることから、早急に治療を行わなければ命に関わることもあります*1。
なお、心筋梗塞などが原因で心臓のポンプの働きが悪くなった状態を「心不全」と呼びます*1。心不全は症状の程度によって4つに分類されており、安静時にも動機や息切れが起こる重度な状態(IV度)となった場合、適切な治療を受けないでいると2年以内に50%の方が亡くなるといわれています*2。
2023年の厚生労働省の人口動態データによると、日本人の死因の第2位は心疾患(心臓に起こる病気の総称)で、死因全体の14.7%を占めています*3。また、心疾患のうち心筋梗塞を発症した方の死亡率は25.6%、心不全の死亡率は81.9%に上ります*3。なお、突然死(病気を発症後24時間以内に亡くなること)の中でも多いのが心臓の病気による急性心臓死であり、その大半が心筋梗塞・狭心症とされています*4。
心筋梗塞の発症は40代から増加し、70~80代前半が最も多い
心筋梗塞は決して高齢者だけの病気ではありません。厚生労働省が2023年に発表した患者調査によると、心筋梗塞および狭心症(虚血性心疾患)の発症者は、40代から徐々に増加し始め、とくに70~80代前半で最も多くみられます*5。最近では、生活習慣の欧米化や高ストレス社会、運動不足などを背景に、若年者の発症も懸念されています。
どう違う? 「心筋梗塞」と「狭心症」
心筋梗塞と同じく、冠動脈と呼ばれる心臓を覆う血管に問題が生じる病気に「狭心症」があります。いずれも原因の多くは「動脈硬化」によるものです*1。
動脈硬化とは、加齢などにより動脈が硬くなったり、血管の壁にプラーク(脂肪などが固まったもの)が発生し血管の内部が狭くなったりしている状態のことです。血管が狭くなり心筋への血液供給が不足した状態が「狭心症」です。プラークが破れ血栓(血の塊)ができ、冠動脈の血管が完全に詰まると、「心筋梗塞」が発症します*1。
心筋梗塞から命を守るために、前兆を見逃さず、早期の治療開始が大切
心筋梗塞は突然発症するイメージがあるかもしれませんが、血管が完全に詰まる前に起こる前兆となる症状がみられることもあります*6,*7。実際、心筋梗塞で入院した患者のうち、約半数に前兆の症状(不安定狭心症)が認められたとの報告があります*7。次項で紹介する前兆の症状のような異変を感じたら、すみやかに医療施設を受診しましょう。この段階で適切な治療を受ければ、心筋梗塞の発症を予防できる可能性が高まります。
前兆となるような症状がみられず、突然心筋梗塞を発症した場合は、ただちに救急搬送を要請しましょう。少しでも早く治療につなげ、心筋の壊死の範囲をできるだけ小さくとどめることで、心機能の低下や心不全などの後遺症のリスクを軽減できます*8。目安として、発症から2時間以内に治療を開始できれば、心筋を救う効果が大きくなるとされています*9。他方、治療が30分遅れるごとに1年後の死亡率の相対リスクが増加するとの報告もあるため*10、心筋梗塞を疑ったら迷わず救急車を呼びましょう。
心筋梗塞の初期症状ー見逃されやすい前兆から緊急時の症状まで
心筋梗塞の前兆をチェック! 胸痛や肩の痛み、吐き気に要注意
心筋梗塞は、突然発症する前に、以下のような前兆が現れることがあります*6,*7。
- 胸の痛み・圧迫感・締めつけ感
- 腕や肩、歯、あごの痛み
- 吐き気、胸やけ
- 冷や汗
- 息切れ、疲労感
胸の中心や全体、もしくは背中側に、締めつけられるような痛みを感じることが多いとされています。「ズキズキ」「チクチク」といった痛みではなく、息が詰まる感じ、焼けつくような感じと表現されることもあります*11,*12。また、腕や肩、歯やあごなど、胸部以外の箇所が痛むこともあります。このほか、原因不明の吐き気や冷や汗、息切れなども注意が必要です。心筋梗塞の前兆は個人差が大きく、このような心臓周辺ではない症状だけがみられることもあります*12。
これらの症状が、一瞬~数秒で消えるのではなく、数分~10分、長くても20分程度みられた場合は心筋梗塞の前兆の可能性があります*7,*11。また、安静にしていても痛みがある、痛みを感じる回数や継続時間が少しずつ長くなっている場合などは心筋梗塞の発症リスクが高い状態だと考えられます*9。今までにない症状を自覚したら、すぐに循環器内科のある病院を受診して検査を受けましょう。心筋梗塞の前段階(不安定狭心症)とわかれば、治療して心筋梗塞の発症を未然に防ぐことができます*7,*12。
なお、チクチクとした痛み、さわったときや体勢を変えたとき、咳や深呼吸をしたときに感じる胸の痛みは、心筋梗塞の前兆である可能性は低いと考えられます*11,*12 。
心筋梗塞発症時の症状は、激しく強い胸の痛み
心筋梗塞を発症すると、激しい胸の痛みや息苦しさ、冷や汗や吐き気といった前兆と同じような症状が20分以上から数時間と長時間に及ぶことが多いです*11。また、男性は冷や汗をともなうことが多く、女性は吐き気、呼吸困難感が多いとされています。このほか、女性は肩や首、あご、背中、腕などに痛みが現れることも多いとされています*11,*12。
ただし、症状は個人差が大きく、症状が強いほど重症ということではありません。また、高齢の方や糖尿病の方は症状に気づきにくい場合があり、心筋梗塞を発症しても痛みを自覚しない方もいます(「自覚症状がない「無痛性心筋虚血」にも要注意」参照)*11。
心筋梗塞は「冬場の早朝」に多い
心筋梗塞は早朝に発症することが多く、とくに冬場に多いことが知られています。この理由として、朝に血圧が上がりやすいこと、冬場は暖かい室内と寒い室外との温度差が大きく心臓に負担がかかることが考えられています*13,*14。
自覚症状がない「無症候性心筋虚血」にも要注意
心筋梗塞や狭心症は、時に胸の痛みなどの自覚症状がない「無症候性心筋虚血」として発症することがあり、これは高齢者や糖尿病の方に多いとされています。高齢者の場合、たとえば強い疲れや食欲低下など、全体的な体調不良を訴えることが多く、一方で糖尿病の方は、わずかな息苦しさ程度の症状しか自覚できないことがあります*12。
無症候性心筋虚血では典型的な胸痛が出現しないため、心筋梗塞と気づきにくく、心不全に進行するリスクが高まります。高齢者や糖尿病の方は、いつもと少し体調が違う、といった変化にも日頃から注意を払いましょう。また、定期的に健康診断や人間ドックで心電図などの検査を受診し、心筋梗塞や狭心症を発見することも大切です。気になる症状がある場合は、すぐに循環器専門医に相談しましょう。
心筋梗塞になりやすい人の特徴は?
心筋梗塞になりやすいリスク因子として、代表的なものは以下のとおりです*11。
- 高血圧
- 高血糖
- 高コレステロール血症
- 喫煙
- 心筋梗塞になった家族がいる
高血圧や高血糖、高コレステロール血症、喫煙は、心筋梗塞の原因となる「動脈硬化」を進行させます。血圧や血糖値、コレステロール値が高い状態が続くと、血管が傷つきます。タバコに含まれる有害物質も血管を傷つけます。そして、傷ついた血管の壁に、血液中のコレステロールが蓄積し、プラークができることで、血管内が狭くなっていきます*15。また、両親やきょうだいなど血縁者に、若くして発症した方(男性55歳未満、女性65歳未満)がいる場合も注意が必要です*11。その理由として、生活習慣が似ていることや遺伝的な要因の関わりが考えられています*16。
上記のほか、ストレスが心筋梗塞の発症の引き金となることがあります。働き盛りの男性の場合、深夜の就業中や、仕事が憂うつになりがちな月曜日の発症が多く、高齢女性は家事負担が集中しやすい週末の土曜日に発症するケースが多いことが知られており、ストレスとの関連性が示唆されています*17。
心筋梗塞の予防法
定期的な健康診断の受診
心筋梗塞の予防において、定期的な健康診断の受診が大切です。血圧測定では高血圧の有無を、血液検査では血糖値やコレステロール値などを確認しましょう。これらの項目で異常(基準範囲外)の値が出た場合は、心筋梗塞を発症するリスクが高まる可能性があります。かかりつけ医や必要に応じて循環器専門医に相談し、生活習慣の改善に努めましょう*14。
食事や生活習慣の改善
心筋梗塞のリスク因子である動脈硬化を予防するためには、日々の食事や生活習慣の見直しが欠かせません。以下のことから取り組んでみましょう*15。
- 禁煙する
- 減塩など、健康的な食生活を心がける
- 節酒する
- 適度な運動を習慣化する
たばこはまったく吸わないことで予防効果を発揮します。喫煙している方は、本数を減らすのではなく、禁煙しましょう。また、減塩をはじめとした健康的な食生活は、動脈硬化の予防につながります。動物性脂肪(バターなど)や脂身の多い肉は避ける、肉よりも魚を食べる、白米よりも玄米を食べる、野菜や海藻、きのこを食べる、糖質が少ない果物をとる、お菓子やジュースは控えるなど、工夫できることから始めてみましょう。お酒の摂取量は、1日あたりビールは1缶(350mL)、日本酒なら1合以下にすることがすすめられています*15。
運動面では、ウォーキングや水泳などの有酸素運動とスクワットやダンベルなどの筋肉に負荷をかける運動を両方とも行うことが効果的とされています。頻度は週3日以上を心がけ、習慣化するようにしましょう*15。
心臓ドックの受診
心臓ドックは、心臓病(狭心症や心筋梗塞など)の発生を未然に防ぐこと、また早期に治療することで重症化を防ぐことを目的とした専門ドックです。健康診断や基本的な人間ドックで心電図検査を受診できることもありますが、初期の異常な波形は心電図で見つけられないこともあります。心臓ドックでは、運動負荷心電図検査、冠動脈CT検査、心臓MRI検査など、より心臓病を詳細に調べられる検査をまとめて受診できます。
運動負荷心電図検査とは、ランニングマシーンのような運動装置を使いながら心電図を行う検査で、通常の心電図検査よりも不整脈や初期の狭心症を見つけられます。また、冠動脈CT検査や心臓MRI検査は、冠動脈の狭さや血栓の有無を画像で評価する検査で、より詳細に心臓の血管の状態を調べることができます。
定期的な心臓ドックの受診で、心臓の状態や動脈硬化の進行度を把握しておくことは、心臓病を予防するうえで非常に重要です。前項で紹介した「食事や生活習慣の改善」を継続するためのモチベーション維持にもつながります。心臓病予防のために、定期的な心臓ドックの受診を検討してみてください。
参考資料
*1.日本心臓財団 虚血性心疾患とは
*2.日本心臓財団 心不全の予後はがんより悪い!?
*3.厚生労働省 令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況
*4.東京都保健医療局 東京都監察医務院 突然死の中で最も多い急性心臓死
*5.厚生労働省 令和5年(2023)患者調査の概況
*6.国立循環器病研究センター 不安定狭心症
*7.日本循環器学会 STOP−MI(心筋梗塞)キャンペーン
*8.小室一成「心不全の予防と新しい治療」日本内科学会雑誌 2017; 106(9)
*9.東京都CCU連絡協議会 急性心筋梗塞
*10.Giuseppe De Luca, et al. Time Delay to Treatment and Mortality in Primary Angioplasty for Acute Myocardial Infarction: Every Minute of Delay Counts. Circulation, 2004; 109(19)
*11.日本循環器学会他「急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版)」
*12.循環器病研究振興財団「知っておきたい循環器病あれこれNo.156 脳卒中・心筋梗塞の前触れと早期対策」
*13.長寿科学振興財団 健康長寿ネット 心筋梗塞
*14.循環器病研究振興財団「知っておきたい循環器病あれこれNo.92 心筋梗塞が起こったら」
*15.日本動脈硬化学会「動脈硬化を知る×動脈硬化を予防する食事」
*16.Kawano H, et al. Japanese Acute Coronary Syndrome Study (JACSS) Investigators. Sex differences of risk factors for acute myocardial infarction in Japanese patients. Circ J, 2006; 70(5)
*17.厚生労働省 e-ヘルスネット 心筋梗塞発症の危険因子:抑うつとストレス