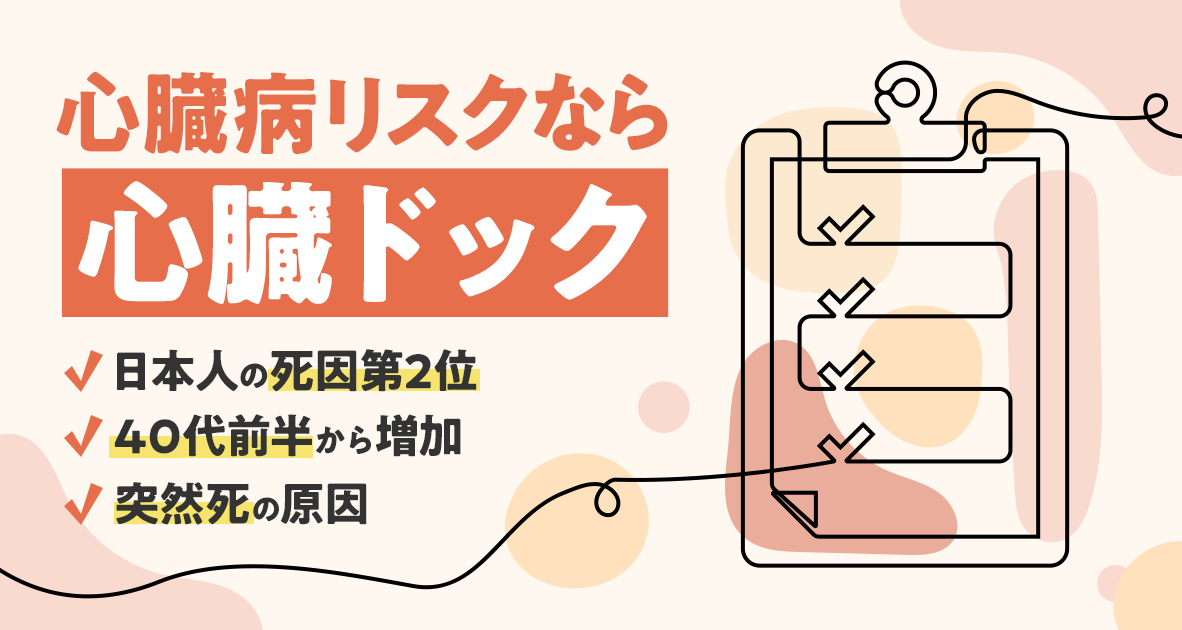心臓ドックは、心臓の病気(心疾患)を早期発見するための専門ドックです。心疾患は、いったん発症すると死に至るリスクがあります。本記事では、心臓ドックの詳細や検査の種類のほか、費用や受けたほうがよい人、医療施設の選び方などを解説します。
★こんな人に読んでほしい!
・心臓ドックに興味がある方
・生活習慣病を指摘されたことのある30代以上の方
・心臓ドックの費用相場や医療施設の選び方を知りたい方
★この記事で解説していること
・心疾患(心臓病)は日本人の死因第2位、発症者は40代前半から増加
・突然死のうち多いのが急性心臓死であり、その大半が心筋梗塞や狭心症である
・心臓ドックを受けたほうがよい方は生活習慣病のある方や喫煙者、生活習慣の乱れがある方
・心臓ドックでわかる病気はおもに、心筋梗塞、狭心症、心不全、不整脈、弁膜症、心筋症、大動脈瘤など
・心臓ドックの費用は、保険適用外で2~5万円
目次
心臓ドックとは? 健康診断・人間ドックとの違い
心臓ドックとは?
心臓ドックとは、心臓超音波(エコー)検査や心臓CT検査、血圧脈波検査などの検査を組み合わせ、心臓内部の構造や機能、心臓をおおう筋肉の動きや血管の流れなどを多角的に調べる専門ドックです。これにより、発症前の心臓の病気を発見するだけでなく、リスクを知ることができ、早期発見・早期治療、あるいは発症の防止へとつなげて死に至る可能性を軽減することができます。
専門ドックは人間ドックのひとつですが、身体を網羅的に調べる基本的な人間ドックとは異なり、複数の検査を組み合わせて特定部位をより詳しく調べ、病気の早期発見や兆候の発見、リスクなどを診断するためのものです。心臓ドックでは、心不全・虚血性心疾患(代表例は狭心症や心筋梗塞)・心臓弁膜症などの心臓の病気の有無や兆候を知ることができます。心臓ドックでわかる病気は、各医療施設のプランに含まれている検査の種類によって異なります。詳細は「心臓ドックでわかる病気と検査の種類」で解説します。
なお、心臓の病気に関してよく耳にする言葉として「心臓病」があります。心臓病とはひとつの病気を指すのではなく、心臓の構造や機能(働き)の異常、周辺の血管を起因として生じる病気の総称です*1。さらに、同様の言葉として「心疾患」があり、このふたつの言葉は一般的にほぼ同義と解釈して問題ありません。本記事では以降、「心疾患」と記載します。
心臓ドックは意味がない? 受診の必要性
2024年の厚生労働省の人口動態データによると、日本人の死因は、がんに次いで心疾患(心臓病)が第2位となっており、死因全体の14.1%を占めています*2。また、突然死(病気を発症後24時間以内に亡くなること)のうち多いのが急性心臓死であり、その大半が心筋梗塞・狭心症とされています*3。これらから、発症前にリスクを把握し、未然に防ぐことが重要であるとわかります。
心筋梗塞や狭心症の多くは、動脈硬化に起因します*4。動脈硬化とは、加齢などにより動脈が硬くなったり、血管の壁にプラーク(脂肪などが固まったもの)が発生し血管の内部が狭くなったりしている状態のことです*5。血管が狭くなると、心筋への血液供給が不足したり、血栓が生じて血管が詰まりやすくなったりします。
同じく動脈硬化に起因する病気に、脳血管疾患があります。脳血管疾患とは脳の血管トラブルによって引き起こされる病気の総称で、代表的なものが脳卒中(脳梗塞・くも膜下出血・脳出血)です。脳血管疾患の有無を調べる専門ドックは脳ドックです。一方、心臓ドックは、現在の心臓の状態を明確に知り、狭心症や心筋梗塞の発症前にリスクを評価できる手段のひとつでありながら、脳ドックよりも受診者数が少ないのが現状です(MRSO2023年および2024年データより)。日本人の死因第2位であり、増加し続けている心疾患を予防するため、心臓ドックはもっと注目されてよい専門ドックと言えます。
健康診断や基本的な人間ドックの心電図検査では、初期の心臓病を見落としやすい
職場の定期健康診断や40歳以上が受診する特定検診には、心機能の検査項目として心電図検査があります。しかし、いずれも、心電図検査について「医師の判断によって省略可」もしくは「医師が必要と認めた場合に実施」とされています*6,*7。よって、医師の判断次第で実施されない場合があります。
自由診療である人間ドックでは、心電図検査が含まれていることが一般的です。日本人間ドック・予防医療学会が定める人間ドックの「基本検査項目」には、心電図および心拍数が掲げられています*8。
心電図検査は、心臓の筋肉(心筋)が発する電気信号を拾って波形として記録する検査です*9-*11。受診者はベッドに仰向けになってじっとしているだけなので、簡便な検査です。
心電図検査にはいくつかの種類がありますが、心臓ドックで行われることが多いのが「運動負荷心電図検査」です。これは、運動によって心臓に負荷をかけ、運動前後、あるいは運動時の心電図を記録し、安静時のみではわからない心電図の変化をみる検査です*9,*10。なお、心臓ドックでは、異なる複数の検査を行うことで、各検査の不得意分野を補完しながら総合的に診断します。
このように、心疾患(心臓病)になるリスクを正確に評価したり、初期の心疾患を見つけたりする点では、健康診断と比較すると心疾患に特化した検査を組み合わせている心臓ドックに優位性があります。
心臓ドックでわかる病気と検査の種類
心筋梗塞
心筋梗塞とは、心臓に血液を運ぶ冠動脈がプラークや血栓で完全に詰まり、血液が心筋(心臓を動かす筋肉)まで行き届かなくなる病気です*4,*12。原因は動脈硬化の進行で、プラークは脂肪やコレステロールのかたまりです。心臓に血液が流れなくなると、時間の経過とともに心筋は壊死します。多くの場合、強い痛みが症状として現れ、治療が遅れると死に至る可能性があります。なお、高齢者や糖尿病患者においては、体内で異変が起こっていても症状のない「無症候性心筋虚血」という状態に陥っていることもあります*13。
【心臓ドックで心筋梗塞を見つけるためのおもな検査*4,*14】
- 心電図検査(安静時心電図検査)
- 心臓超音波(エコー)検査
- 冠動脈CT検査(心臓CT検査)
- 冠動脈MRI検査(心臓MRI検査)
- 血液検査※補助検査
- 血圧脈波検査※補助検査
など
心筋梗塞の詳細は、下記記事でまとめていますのでご覧ください。
狭心症
狭心症には大きく、労作(ろうさ)性狭心症(安定狭心症)、不安定狭心症、冠攣縮(かんれんしゅく)性狭心症があります。
労作性狭心症と不安定狭心症はいずれも、動脈硬化によるプラークなどで冠動脈が狭窄し、充分な血液が心臓に供給されない病気です*4。労作性狭心症は、日常的な軽い身体活動(階段を昇る、坂道を登る、重いものを持ち上げる等)で胸の痛みや苦しさなどの発作が現れ、安静にしていると治まります*15,*16。一方、不安定狭心症は、安静時でも発作が現れたり頻回になったりする病気で、冠動脈が完全には閉塞していないものの、心筋梗塞の前段階とされます*17。
冠攣縮性狭心症は動脈硬化の進行過程であるといわれており*15、就寝中やとくに明け方などの安静時、痙攣によって冠動脈が一時的に狭窄し、胸の痛みや苦しさなどの発作が現れます。発作が起こっていないときは、検査を行っても狭窄が認められないことが特徴とされています*18。
【心臓ドックで狭心症を見つけるためのおもな検査*4,*14,*16】
- 運動負荷心電図検査
- 心臓超音波(エコー)検査
- 冠動脈CT検査(心臓CT検査)
- 冠動脈MRI検査(心臓MRI検査)
- 血液検査※補助検査
- 血圧脈波検査※補助検査
など
狭心症については、下記記事もご覧ください。
心不全
心不全は病気の名前ではなく、心臓の病気や状態の結果、心臓のポンプ機能が低下して全身の臓器に十分な血液を送り出せなくなった状態のことです*19,*20。心不全の原因となる心臓の病気は、心筋梗塞や狭心症、不整脈、弁膜症、心筋症などさまざまです。心筋梗塞や狭心症、突然の不整脈によって心臓の働きが短期間で悪くなった状態を急性心不全、弁膜症や心筋症などで長期にわたって心不全となっている状態を慢性心不全といいます。慢性心不全にはおもに生活習慣病が関わっており、高血圧や脂質異常症、糖尿病などが原因となります*19。
【心臓ドックで心不全を見つけるためのおもな検査*4,*9,*11,*14,*16,*21-23】
- 心電図検査(安静時心電図検査)
- 運動負荷心電図検査
- 心臓超音波(エコー)検査
- 冠動脈CT検査(心臓CT検査)
- 冠動脈MRI検査(心臓MRI検査)
- 血液検査※補助検査
- 血圧脈波検査※補助検査
など
不整脈
不整脈とは、心臓の拍動、つまり心臓の周期的な動き(リズム)が異常である状態のことです*24,*25。不規則、極端に速い、極端に遅いなどの種類があり、それぞれ命に関わるものから放っておいて問題ないものまでさまざまです。そのなかで、放置すると短時間で死亡する危険性がある致死性不整脈、長時間放置すると死に至る可能性のある準致死性不整脈は治療の対象です*25。
【心臓ドックで不整脈を見つけるためのおもな検査*9,*10】
- 心電図検査(安静時心電図検査)
- 運動負荷心電図
など
弁膜症
弁膜症(心臓弁膜症)とは、心臓にある4つの部屋の出入口にある弁に異常が起こっている病気です*26。全身から戻ってきた血液(静脈血)は右心房から右心室を通って肺へ、肺で酸素を取り込んで戻ってきた血液(動脈血)は左心房から左心室を通って全身へ送られていきます。4つの部屋は一方通行で、各部屋の間にある弁が開いたり閉じたりして逆流を防いでいます*21。これら弁の動きが悪くなると出口の狭窄や逆流が生じ、心不全の原因になります*20。
【心臓ドックで弁膜症を見つけるためのおもな検査*21】
- 心電図検査(安静時心電図検査)
- 心臓超音波(エコー)検査
など
心筋症
心筋症とは、心筋自体の異常によって、心臓の働きを維持できなくなる病気の総称です*22,*23。心臓はおもに筋肉でできており、その異常の原因はいくつかのタイプにわかれます。具体的には、心筋が肥大して心室が圧迫されることで充分な血液が送り出されにくくなる肥大型心筋症、心筋の収縮力が低下することで心室が拡張して心筋が薄くなる拡張型心筋症などがあります*22。なお、心不全患者のうち、27%が拡張型心筋症だったという報告があります*27。
【心臓ドックで心筋症を見つけるためのおもな検査*22,*23】
- 心電図検査(安静時心電図検査)
- 心臓超音波(エコー)検査
- 冠動脈MRI検査(心臓MRI検査)
など
大動脈瘤
大動脈瘤とは、体内でもっとも太い血管である大動脈がなんらかの原因でふくらみ、こぶのような状態になっていることを指します*28-30。大動脈は心臓から送り出された血液が最初に通る血管であり、高い圧力がかかります。大動脈瘤の主因は動脈硬化とされており、動脈硬化によって弱く薄くなった血管の壁が圧力によってふくらみ、一般的に1.5倍の太さになった状態が大動脈瘤とよばれます*29。胸部大動脈瘤の60%は無症状とされており**29、破裂すると命に関わります。
【心臓ドックで大動脈瘤を見つけるためのおもな検査*29】
- 心臓超音波(エコー)検査
- 冠動脈CT検査(心臓CT検査)
- 血圧脈波検査※補助検査
- 血液検査※補助検査
など
各検査の詳細は、次項で解説します。
心臓ドックの検査
心臓ドックのプランに含まれている検査は、医療施設によって異なります。ここでは心臓ドックでおもに行われている検査について解説します。おおまかな検査の使い分けは以下を参考にしてください。
- 不整脈、狭心症を簡便に調べたい方:心電図検査(安静時心電図検査)
- 運動後の胸の苦しさが気になる方:運動負荷心電図検査
- 心不全を詳細に調べたい方:心臓超音波(エコー)検査、冠動脈MRI検査(心臓MRI検査)
- 狭心症や心筋梗塞のリスクを詳細に調べたい方:冠動脈CT検査(心臓CT検査)、冠動脈MRI検査(心臓MRI検査)
- 動脈硬化、心不全を簡便に調べたい方:血圧脈波検査、血液検査
心電図検査(安静時心電図検査)*9,*10
【検査の目的】
心臓の電気的な活動を波形として記録することで、心臓の状態を評価すること
【特徴】
心電図検査は、心臓の筋肉(心筋)が発する電気信号を拾って波形として記録する検査です。安静時心電図検査や12誘導心電図検査ともよばれます。非常に簡便な検査ですが、一部の心疾患は、進行していない段階や安静時では発作が出ず、波形に変化がみられないことがあります。
【検査方法】
ベッドに仰向けになり、素肌の手足や胸部に電極クリップをつけた状態で静かに過ごします。電極から電気を流すのではなく、心臓の筋肉が発する電気信号をキャッチする検査です。
【検査時間】
5~10分程度
【注意事項や特記事項】
- 電極クリップを素肌に装着するため、ストッキングやタイツは脱ぐ必要がある
- 時計やネックレスはつけていても問題ない
運動負荷心電図検査*9,*10,*16
【検査の目的】
運動時に虚血(必要量の血液が供給されていない状態)を示唆する心電図の変化がないかの観察
【特徴】
運動負荷心電図検査は、心臓に負荷をかけた際に心臓が正常に動作しているかどうかを評価することができます。また、運動途中や運動後の心臓の様子を運動前と比較することで、安静時にはわからない心臓の変化を知ることができるため、初期の狭心症や特定の心疾患を見つけられる可能性が高まります。
【検査方法】
心電図の電極を胸に貼った状態で、運動前後、また運動時の心電図を記録します。運動用の器具には、専用の昇降ステップやランニングマシーン、自転車こぎのような装置があります。年齢や性別などを考慮しながら心臓に負荷をかけていきます。
【検査時間】
30分程度
【注意事項や特記事項】
- 検査直前の食事や喫煙は不可
- 運動できる衣類に着替える必要がある
心臓超音波(エコー)検査
【検査の目的】
心臓の内部構造・心臓壁の動き・弁膜の状態や血流に関する情報をリアルタイムに調べるほか、心臓のポンプ機能が正常かどうかなど緊急性のある重要な情報の画像評価
【特徴】
心臓超音波(エコー)検査は、超音波を用いて心臓の内部構造・心臓壁の動き・弁膜の状態や血流に関する情報を短時間でリアルタイムに調べられる検査です。息止めも少ないので、高齢者でも安心して受けることができます。血管内を観察することはできないので、血管の狭窄が心配な方は冠動脈CT検査や冠動脈MRI検査と組み合わせることをおすすめします。
【検査方法】
ベッドに横向きに寝た状態で胸の上にゼリーを塗り、プローブ(探触子)と呼ばれる装置をあてて画像を取得、モニターで心臓の様子を観察します。
【検査時間】
20~30分程度
【注意事項や特記事項】
- 検査者の技量に左右される
- 冠動脈内の狭窄を評価するのは困難
心臓超音波(エコー)検査の詳細は下記記事をご覧ください。
冠動脈CT検査(心臓CT検査)*31
【検査の目的】
放射線を用いて、冠動脈の走行、狭心症や心筋梗塞の原因となる血管の狭さ(狭窄度)、血栓の有無などを調べる
【特徴】
冠動脈CT検査(心臓CT検査)は、放射線を用いて、心臓の血管の画像を撮像する検査です。また近年では、心電図をCT装置と連動させることで心臓の拍動に合わせてブレの少ない高精細な画像を撮影できる320列CT装置も増えています。施設によっては、CTの3D画像を示しながら問診を行ってくれるところもあります。
【検査方法】
心電図の電極を胸に貼って、仰向けの状態で装置に寝ます。CT検査の途中で、造影剤と呼ばれる薬剤を静脈から注入することで、より鮮明に冠動脈をうつしだします。
【検査時間】
10分程度
【注意事項や特記事項】
- 放射線による被曝がある
- 造影剤を使う場合、まれに副作用を起こすことがある
- 気管支喘息やヨードアレルギーの場合は検査できないことがある
冠動脈MRI検査(心臓MRI検査)*32
【検査の目的】
左室の壁運動の評価、冠動脈の走行や血管の狭さ、動脈硬化、血栓の有無などの評価
【特徴】
冠動脈MRI検査(心臓MRI検査)は、MRI/MRA装置を使った検査です。医療施設によって造影剤を使用しないプランと使用するプランがあり、近年は装置の発達により、検診段階では造影剤を使用しないことが一般的になっています*33。造影剤は副作用が起こるリスクがあるためです。造影剤を使用しない場合、大動脈に血液を送り出す左心室や、心臓の筋肉に血液を送っている冠動脈の状態を立体的に撮像することができます。造影剤を使用する場合、さらに心筋の繊維化を見つけることができるため、早期の心筋梗塞を見つけられるという強みがあります。
【検査方法】
仰向けで装置に寝てドーム状の装置の中に入ります。検査が始まると、息止め指示に合わせて呼吸を止めます。
【検査時間】
1時間前後
【注意事項や特記事項】
- ペースメーカーや人工内耳など体内に金属が埋め込まれていると検査を受けられないことがある
- 被曝がない
- 造影剤を使う場合、まれに副作用を起こすことがある
- 閉所恐怖症の方は圧迫感を感じることがある
- 検査中に騒音が続くため不快に感じることがある
- 検査時間が長い
- 検査中の息止め回数が多い
血圧脈波検査*34
【検査の目的】
動脈硬化の進行度を調べる
【特徴】
血圧脈波検査は、手と足の血圧や脈波を測定することで動脈硬化の程度を調べる検査です。ベッドに仰向けになり、両上腕部・両足首の計4ヶ所の血圧を同時に計測します。動脈の硬さ(CAVI)と血管の狭窄の程度(ABI)を評価します。一般的な血圧測定同様、薄着であれば着衣のまま計測が可能です。
【検査方法】
仰向けに寝て、両手足に専用器具をつけて脈波や血圧を測定します。同時に心音を記録します。
【検査時間】
5~10分程度
【注意事項や特記事項】
- 腕や足に怪我をしている人には不向き
- 透析、乳がんの手術後など強い圧をかけられない人は検査対象外のことがある
血液検査
【検査の目的】
動脈硬化、心不全、心筋梗塞のリスクなどの評価
【特徴】
心臓ドックにおける血液検査では、心不全マーカーであるBNPやNT-pro BNP、コレステロール値、血糖値などを調べることが多いです。BNPやNT-pro BNPは、心臓に負荷がかかった際に放出されるホルモンの一部やその副産物で*35、心不全の可能性を調べる手がかりとして広く用いられています。その他、動脈硬化の進行を判定し、心筋梗塞や脳梗塞の発症リスクを評価するLOX-index®を心臓ドックの血液検査に取り入れている医療施設もあります。
【検査方法】
静脈から採血をします。
【検査時間】
5分程度
【注意事項や特記事項】
医療施設によって血液検査の項目が異なる
心臓ドックを受けたほうがよい方
生活習慣病のある方や喫煙者は心臓病のリスクあり
心臓ドックを受けたほうがよい方は、高血圧・糖尿病・脂質代謝異常などの生活習慣病の方、喫煙者、心疾患(心臓病)の家族歴がある方です。なお、運動時に胸が痛むなどの自覚症状がある方は、すみやかに診察を受けましょう。
心疾患で亡くなった方のうち、もっとも多いのは「心不全(42.9%)」で、以降は「その他の虚血性心疾患※1(17.4%)」、「不整脈および伝導障害(15.6%)」、「急性心筋梗塞※2(13.4%)」と続きます*2。
※1.その他の虚血性心疾患:心筋梗塞を除く虚血性心疾患のこと。おもに狭心症を指す。
※2.急性心筋梗塞:発症から間がなく、心筋壊死が急速に進行しつつある病態。心筋梗塞のほとんどを占める。
「心不全」で解説した通り、心不全自体は病気の名前ではなく、心臓になんらかの異常が起こっている状態を指します。心不全の原因となる心臓の病気は、心筋梗塞や狭心症、不整脈、弁膜症、心筋症などさまざまです。このうち心筋梗塞や狭心症など、心臓のポンプ機能の働きが悪くなる病気全般は虚血性心疾患とよばれ、主因は動脈硬化です*4。動脈硬化の危険因子は、加齢・喫煙・脂質異常症・高血圧・飲酒・糖尿病などとされており*5、ほとんどが生活習慣に関わっています。その他、動脈硬化による疾患は遺伝するとされています*36。
心臓病は40代前半から増加、30代のうちにリスクを知って予防しよう
虚血性心疾患(狭心症および心筋梗塞)は高齢者の病気というイメージがあるかもしれません。厚生労働省が2023年に発表した患者調査によると、虚血性心疾患(狭心症および心筋梗塞)の発症者は70~80代前半がピークですが、40代前半から増加していきます*37。近年、生活習慣の欧米化や高ストレス社会、運動不足などを背景に、若年者の発症が懸念されています。リスクを把握することは予防につながります。生活習慣の乱れに心当たりがある方は、30代であっても心臓ドックを検討してもよいでしょう。
生活習慣のセルフチェックをしてみよう
日本循環器学会では、心不全に該当しない方への生活習慣チェックとして、下記17項目をまとめています*38。チェックがついた方は生活習慣の改善が必要です。
日本循環器学会 生活習慣チェックシート
- 運動不足である
- ご飯やパンなど炭水化物の摂取量が多く、食事のバランスが偏っている
- みそ汁やスープを1日2回は飲む
- ご飯には梅干しや漬物が欠かせない
- 市販のお惣菜やインスタント食品をよく利用する
- 麺類の汁を半分以上飲む
- 魚の干物やハム、ウィンナーなどの加工食品が好き
- 脂っこいものが好き
- 甘いものが好き
- 毎日お酒を飲んでいる
- タバコを吸っている
- 生活が不規則である
- 睡眠時間が5時間未満である
- いびきが大きい
- 収縮期血圧が130を超えている
- HbA1cが6.0%を超えている
- BMIが30を超えている
心臓ドックを受けた方の感想
マーソには、人間ドックや専門ドックを受診した方の感想が多数寄せられています。その中から、心臓ドックを受けたみなさんの声を紹介します。
東京都在住(47歳・男性)
循環器に特化した人間ドックを初めて受診しました。心臓や、血管を検査していただき、今の状況を把握することができました。
埼玉県在住(57歳・女性)
心機能への不安があったため心臓ドックを受診しました。大変満足がいくものとなりました。
東京都在住(54歳・男性)
CTで見る心臓ドックを初めて受けました。 心疾患があるわけではないのですが、動脈硬化など詳しく見ていただきました。
人間ドックを受診したきっかけや検査結果など、よりリアルな体験談は、こちらからお読みいただけます。
心臓ドックの費用は2~5万円で、施設によって異なる
保険適用外で、費用は2~5万円
心臓ドックは自由診療のため保険適用外で、費用目安は2~5万円です。このうち、低価格の心臓ドックでは下記のような比較的簡便な検査が単体あるいはセットで行われています。
- 心電図検査
- 心臓超音波(エコー)検査
- 血液検査
- 血圧脈波検査
費用目安のうち、中~高価格帯の心臓ドックでは、精度の高い医療機器や心疾患(心臓病)の鑑別に特化した技術を必要とする以下の検査が組み込まれていることが多いです。
- 運動負荷心電図
- 冠動脈CT検査(心臓CT検査)
- 冠動脈MRI検査(心臓MRI検査)
費用と得られる情報量は比例していることを理解しておきましょう。
補助金の有無は加入している健康保険組合に確認を
心臓ドックは原則保険適用外ですが、職場等で加入している健康保険組合から心臓ドックの補助金を受けられる場合があります。被保険者なら2~3万円程度補助金を受けられる場合もあります。心臓ドックの補助金制度の有無は健康保険組合次第ですが、被保険者の扶養者も補助金対象になる場合もありますので、補助金制度が使えるかどうか健康保険組合に確認してみるといいでしょう。
おすすめの医療施設の選び方
受けたい検査項目に対応しているかどうか
心臓ドックは施設によって検査の組み合わせが変わります。そのため、自分が受けたい検査内容に対応している施設を選ぶことは重要なポイントです。
たとえば、血液検査の項目のひとつであるBNPは心臓のダメージ具合が評価できるため、心不全や心臓腫瘍を調べたい方に有効な検査項目です。しかし、心臓ドックの項目に血液検査が入っているからと選んだつもりが、じつは検査項目にBNPが入っていなかったために知りたかったことが評価できないという場合もあります。
心臓ドックの施設を選ぶ際は、検査内容まで十分に確認して選ぶようにしましょう。
循環器専門医がいるかどうか
循環器専門医※とは、日本循環器学会が定める資格で下記を含めたいくつかの条件を満たした医師にのみ与えられる資格です*39。すべての医療施設で循環器専門医による問診があるわけではありません。
- 日本の医師免許を有している
- 内科専門医、外科専門医、小児科専門医のいずれかの資格を有している
- 自らも禁煙を行っている
- 循環器領域の研修(3年以上)を修了している
- 循環器専門医の筆記試験に合格している
循環器に特化した知識と経験を持っている循環器医師が問診を行っている施設は限られるため、心臓ドックに力を入れている施設かどうかの目安にもなります。
※循環器専門医:2025年3月現在、日本専門医機構による新制度「循環器内科専門医」に移行中。
女性専用のクリニックかどうか
心臓の検査は心電図を胸部に貼ったり、心臓超音波(エコー)検査でゼリーを胸部に塗ったりする検査です。心臓ドックを行う医療施設の中には、女性に配慮して問診から診察・検査まですべて女性スタッフを配置していたり、女性専用エリアを設けたりしている施設もあります。
女性専用ではないクリニックでも、希望をすれば女性スタッフが対応してくれる場合もあるので、その場合は事前に問い合わせをして対応可能かどうか確認をしてみてください。
心臓ドックでよくある質問
冠動脈CTと冠動脈MRIはどちらがよい?
CTとMRIは得意領域が異なり、冠動脈の観察においては冠動脈CT検査(心臓CT検査)、心筋(心臓の筋肉)の観察においては冠動脈MRI検査(心臓MRI検査)のほうが有用とされることが多いです。しかしながら、検査時間や被曝の有無などどちらも一長一短あります。それぞれの特徴は下記のとおりです*31,*32。
| 冠動脈CT | 冠動脈MRI | |
|---|---|---|
| 概要 | 心臓と冠動脈をあらゆる角度から 立体的かつ鮮明に描出し、詳細な 冠動脈の狭窄度合いや動脈硬化の 進行度合いを評価する | 心臓と冠動脈を立体的に描出し、 冠動脈や詳細な心筋(心臓の筋肉)の 状態を評価する |
| 画質 | よい。とくに造影剤を使用する場合は 得られる情報が増え、診断精度が高まる | CTと比較すると劣る |
| 検査時間 | 10分程度 | 1時間前後 |
| 音 | なし | あり(工事現場のような騒音) |
| 被曝 | あり | なし |
| 造影剤の使用 | 医療施設によっては使用する | 検診では使用しないことが多い |
心臓ドックを受ける頻度は?
心臓ドックを受けて異常がなく、心疾患(心臓病)のハイリスク群(「心臓ドックを受けたほうがよい方」参照)でない場合、2~5年に1回の頻度での受診を推奨する医療施設が多いです。
心電図検査に引っかかる原因は?
心電図検査(安静時心電図検査)で異常ありとなる原因には、不整脈や狭心症の発作などがあります。それらのなかには、自律神経や検査直前の食事の影響、治療の必要のない不整脈が含まれ、要経過観察となることがあります*40。しかし、要精密検査となった場合は重大な心疾患(心臓病)が潜んでいる可能性があるため、指示にしたがって検査を受けましょう。
狭心症かどうか確かめる方法は?
狭心症かどうかを確かめるためには、心電図検査と画像検査のほか、血液検査等の補助検査を含む心臓ドックをおすすめします。前述の「狭心症」の項もあわせてご覧ください。
【心電図検査】
- 心電図検査(安静時心電図検査)
- 運動負荷心電図検査
【画像検査】
- 心臓超音波(エコー)検査
- 冠動脈CT検査(心臓CT検査)
- 冠動脈MRI検査(心臓MRI検査)
【補助検査】
- 血液検査
- 血圧脈波検査
人間ドックで心筋梗塞かどうかを調べることはできる?
一部の心筋梗塞は、人間ドックに含まれていることの多い心電図検査(安静時心電図検査)で可能性を調べることができます。しかし、安静時に発作のない心筋梗塞や症状の乏しい心筋梗塞を見つけることは難しいです。明確に知りたい場合は、前項の「狭心症かどうか確かめる方法は?」同様、心電図検査と画像検査のほか、血液検査等の補助検査を含む心臓ドックをおすすめします。詳細は前述の「心筋梗塞」および「狭心症」の項もご覧ください。
参考資料
*1.日本心臓リハビリテーション学会 心臓のことを知ろう!Q.1
*2.厚生労働省 令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況
*3.東京都保健医療局 東京都監察医務院 突然死の中で最も多い急性心臓死
*4.日本心臓財団 虚血性心疾患とは
*5.厚生労働省 健康づくりサポートネット 動脈硬化
*6.e-gov 法令検索 労働安全衛生規則 第四十四条
*7.政府広報オンライン 生活習慣病とは?予防と早期発見のために定期的な受診を!
*8.日本人間ドック・予防医療学会 基本検査項目表
*9.日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 心電図、負荷心電図
*10.三重大学医学部附属病院 検査部 心電図検査室
*11.日本心臓財団 心電図とは
*12.国立循環器病研究センター 急性心筋梗塞
*13.日本赤十字社 伊達赤十字病院「だてクロス Vol.6」2018年5月
*14.千葉大学大学院医学研究院循環器内科学、千葉大学病院循環器内科 MRI検査(心臓MRI検査)
*15.日本心臓財団 狭心症とは
*16.国立循環器病研究センター 労作性狭心症(安定狭心症)
*17.国立循環器病研究センター 不安定狭心症
*18.国立循環器病研究センター 冠攣縮性狭心症
*19.日本心臓財団 心不全とは
*20.国立循環器病研究センター 心不全
*21.国立循環器病研究センター 心臓弁膜症
*22.日本心臓財団 心筋症とは
*23.国立循環器病研究センター 心筋症外来
*24.日本循環器学会 不整脈
*25.日本心臓財団 不整脈とは
*26.日本心臓財団 弁膜症とは
*27.日本循環器学会、日本心不全学会「心筋症診療ガイドライン(2018年改訂版)」
*28.国立循環器病センター 大動脈瘤と大動脈解離
*29.日本血管外科学会 血管の病気(血管病)について 胸部大動脈瘤とは
*30.日本ステントグラフト実施基準管理委員会 大動脈瘤のはなし 大動脈瘤ってなあに?―大動脈瘤の基礎知識
*31.国立循環器病研究センター 冠動脈コンピュータ断層撮影装置(冠動脈CT)
*32.高崎総合医療センター 心臓CT・心臓MRIについて
*33.日本医学放射線学会「画像診断ガイドライン2021年版(第3版)」
*34.姫路赤十字病院 血圧脈波検査
*35.日本心臓財団 心不全の診断と検査
*36.多田隼人「遺伝学から動脈硬化性疾患を考える」日本内科学会雑誌 112巻2号 2023年
*37.厚生労働省 令和5年(2023)患者調査の概況
*38.日本循環器学会 生活習慣チェックシート
*39.日本循環器学会「日本循環器学会認定循環器専門医制度規則」2022年改訂
*40.日本心臓財団 貧血とST-T異常