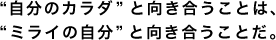40代から定期的に検診したい卵巣がん

日本人の2人に1人がかかり、3人に1人が死亡すると言われているがんは、医療技術の進化により早期発見が可能になってきている。がんの検査方法と治療法シリーズ第6回は、40歳代から増加し、50歳代~60歳代で罹患率のビークを迎える卵巣がんについて紹介する。
卵巣がんの検査では、まず問診と内診が行われる。内診とは、医師が直接指を入れて、卵巣の状態を調べる検査だ。腫瘍による組織の肥大などを、指の感覚を頼りに診査するため、医師の技量が問われる検査となる。何らかの異常が見つかれば、その場で超音波検査を行い、腫瘍の位置や性状などを大まかに調べるケースが多い。
卵巣がんにおけるCTとMRIの比較
内診や超音波検査によって腫瘍が見つかれば、CTやMRIによる画像検査を受けることになる。両検査の特性を比較すると以下のようになる。
| 被曝 | 時間 | 転移 | 組織型 | |
|---|---|---|---|---|
| CT | あり | 短い | 判別可 | 判定困難 |
| MRI | なし | 長い | 判別困難 | 判別可 |
MRIは、大きな音を発生する医療装置のなかに横たわり、長時間、静止しなければならいが、CTは音もなく検査時間も短いため、苦痛は少ないといえる。ただ両検査とも、造影剤を使用する場合は、腕の静脈から注射するため、注射が苦手な人にはつらい。被曝に関しては、CTのみにリスクがあるといえる。
画像から得られる情報は、ほかの臓器への転移と組織型の判別という2点において違いがある。他臓器への転移はCTのほうが判別しやすく、腫瘍の組織型についてはMRIのほうが判別しやすい。これはあくまで比較の問題であって、それぞれの検査に決定的に欠点があるというわけではない。多くの場合、こうした画像検査に加えて腫瘍マーカーを用いた血液検査も行い、診断を確定していく。
卵巣がんの治療法
卵巣がんの治療は、おもに外科療法と化学療法で進められる。卵巣がんは再発率の高いがんで、外科療法のみで対応することは珍しい。ステージⅠ~Ⅱであっても、外科手術によって病変部を切除し、場合によっては抗がん剤による治療を継続していく。ステージⅢ~Ⅳになると、再発や転移のリスクが高まるため、化学療法の重要性が増していく。それと並行して緩和ケアも実施される。

マーソ株式会社 顧問
虎の門病院、国立がんセンターにて造血器悪性腫瘍の臨床および研究に従事。2005年より東京大学医科学研究所探索医療ヒューマンネットワークシステム(現・先端医療社会コミュニケーションシステム)を主宰し医療ガバナンスを研究。 2016年より特定非営利活動法人・医療ガバナンス研究所理事長。

2015年滋賀医科大学医学部医学科卒業。ときわ会常磐病院(福島県いわき市)・ナビタスクリニック(立川・新宿)内科医、特定非営利活動法人医療ガバナンス研究所研究員、東京大学大学院医学系研究科博士課程在学中、ロート製薬健康推進アドバイザー。著書に『貧血大国・日本』(光文社新書)