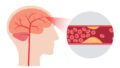認知症は、高齢化社会が進む日本において大きな課題となっています。早期発見と適切な対策が、患者本人とその家族が安心して暮らせる環境を整えるキーポイントとなります。この記事では、認知症の初期症状と対策について解説します。
★こんな人に読んでほしい!
・家族が認知症ではないかと心配している方
・最近、もの忘れが多いと感じている方
・認知症疑いの親との関わりに悩んでいる方
★この記事のポイント
・認知症は、治療や今後の生活設計のためにも早期診断と早期治療が大切
・認知症は早期に発見することで、進行を遅らせることもできる
・認知症の前段階「MIC」の状態で気づけば、健常な状態に戻る可能性もある
・65歳以下でも認知症を発症する場合がある
・認知症によるもの忘れは、体験したことそのものを忘れる、数分前の出来事を忘れるなど、加齢によるもの忘れとは異なる
高齢者に多い認知症。早めの対策が重要
65歳以上の高齢者のうち、約8人に1人は認知症
認知症とは、脳の障害によって記憶力や判断力などの認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態を指します*1。認知症にはいくつかの種類があり、初期症状は若干異なりますが、おもな症状はもの忘れ、時間・場所が認識できない、物事を順序立てて行えないなどで、職場や家庭で行っていた日常的なことができなくなります*2。詳しくは「認知症の種類別、特徴的な初期症状」で後述します。
九州大学の研究によると、2022年時点で65歳以上の高齢者のうち、約8人に1人(患者数443.2万人、有病率12.3%)が認知症を患っていると推計されています。高齢化の進行にともない、2060年には約6人に1人(患者数645.1万人、有病率17.7%)にまで増加すると予測されており、認知症は誰もが関わる可能性がある身近な病気になりつつあります*3。
65歳以下で発症する「若年性認知症」にも注意
認知症は高齢者に多い病気ですが、若い世代でも発症することがあります。65歳未満で発症する認知症を「若年性認知症」と呼びます*4。日本医療研究開発機構(AMED)認知症研究開発事業の調査によると、若年性認知症患者数は全国で約3.57万人と推計されており、50代で発症するケースも珍しくありません*5。
若年性認知症に最初に気づく症状として、「もの忘れが多くなった」「職場や家事などでミスが多くなった」などが上位に挙げられますが*5、疲労やストレス、うつ、更年期障害などによるものと誤解されやすく、診断が遅れやすいことが特徴です*4。
認知症は早期診断・早期治療が大切
認知症を疑ったら、早めに専門医を受診し、適切に治療することが大切です*6。認知症の中でも、正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫、甲状腺機能低下症などを原因とした“治療できる認知症”であれば、早めに症状を治したり、改善したりすることができます*2。また、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症などの“治療が難しい認知症”であっても、早期から治療することで、症状の進行をゆるやかにできます*6。
また、認知症の早期診断は、患者本人や家族にとっても、今後の生活設計の立てやすさにつながります。十分な話し合いの時間をとれることで、介護サービスや経済的なサポート制度などの利用を早くから検討できます*6。患者本人と家族が安心して暮らせる環境を整えやすくするためにも、認知症が疑われたら早めにかかりつけ医などに相談し、必要に応じて認知症外来やもの忘れ外来、脳神経内科、精神科、老年病科、脳神経外科などの専門科を受診しましょう。
認知症の前段階の「MCI」であれば、治せることもある
認知症の前段階である「軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)」の状態で発見できれば、適切な対応により認知機能を改善できることがあります。MCIとは、健常な状態と認知症の中間の状態を指します。認知症は「一人暮らしが困難なほど認知機能が低下した状態」とされていますが、MCIは同年代と比べて記憶力や判断力の軽度な低下がみられることが多いものの、日常生活はどうにか送れていることが多いです*7。65歳以上の高齢者におけるMCIの有病率は認知症者数よりやや多く、15.5%と推計されています(2022年のデータ)*3。
MCIの人が、1年で認知症になる割合は5~15%程度と報告されています*8。一方、1年で約16~41%の人は健常な状態に戻るともいわれており*8、この段階で運動や健康的な食事、認知トレーニングなどを実施し、認知症を予防することが非常に大切です*7。以前よりもの忘れが多くなったり、同年代の人と比べてもの忘れの程度がやや強いと感じたりしたら、念のため認知症専門医に相談しましょう*2。
認知症の初期症状とは?
認知症の種類別、特徴的な初期症状
認知症にはいくつかの種類があり、その種類によって初期症状が異なります。以下が、おもな認知症の種類と特徴的な初期症状です*1,*11。
アルツハイマー型認知症認知症
全体の約6割を占めるもので*5、おもな初期症状は記憶障害です。時間や場所がわからない、順序立てた作業ができない、見たものが何かわからないなどの症状が表れることもあり、ゆっくりと症状が進行していくことが特徴です。
血管性認知症
脳梗塞や脳出血による脳の損傷が原因で起こります。初期症状として、一般的な認知機能障害のほか、歩行障害や手足の麻痺などをともなうのが特徴です。
レビー小体型認知症
一般的な認知機能障害のほか、動きが遅く転びやすくなるパーキンソン症状や、繰り返し見られる幻覚が見られます。
前頭側頭型認知症
脳の前頭葉や側頭葉という部分が原因の認知症です。初期症状は、不適切な行動を起こす、同じ行動を繰り返す、オウム返しの返事が増えるなど、性格や行動の変化が特徴的に見られます。
認知症の初期症状チェックリスト
認知症の初期症状かどうかを簡単に予測する手段のひとつとして、「大友式認知症予測テスト」*9を紹介します。普段の生活を振り返り、どの程度あてはまるか確認してみましょう。
大友式認知症予測テスト
- 同じ話を無意識に繰り返す
- 知っている人の名前が思い出せない
- 物のしまい場所を忘れる
- 漢字を忘れる
- 今しようとしていることを忘れる
- 器具の説明書を読むのを面倒がる
- 理由もないのに気がふさぐ
- 身だしなみに無関心である
- 外出をおっくうがる
- 物(財布など)が見当たらないことを他人のせいにする
採点方法:ほとんどない=0点/時々ある=1点/頻繁にある=2点
認知症予防財団
評価:0〜8点=正常/9〜13点=要注意/14〜20点=専門医などで診断を
「大友式認知症予測テスト」は、当てはまった項目の数とその頻度によって採点する方式のテストです。なお、このテストはあくまでも目安であり、認知症の確定診断には医療施設での専門的な検査が必要です。
また、「認知症の人と家族の会」では、認知症を患った家族がいる方々の経験をもとに、認知症の初期と思われる行動のチェックリストを公開しています*10。こちらも参考にしてみてください。
認知症の人と家族の会 家族がつくった 「認知症」早期発見のめやす(外部サイト)
加齢によるもの忘れと認知症の違い
人は誰しも、年齢を重ねるともの忘れをするようになります。加齢によるもの忘れと、認知症によるもの忘れの違いの一例をまとめました*1,*11。認知症によるもの忘れに当てはまる場合は、すみやかに専門科を受診してください。
<加齢によるもの忘れの特徴>
- 人や物事の名前や漢字が出てこない
- 物の置き場所を忘れる、立ち上がった瞬間に用事を忘れる
- その場で出てこなくても、後になって思い出せる
- もの忘れの自覚がある
- 日常生活に大きな支障はない
など
<認知症によるもの忘れの特徴>
- 体験したことそのものを忘れる
- 数分前の出来事を忘れる
- 置き場所を忘れることが多く、いつも探しものをしている
- もの忘れの自覚に乏しい
- 日常生活に支障をきたす
など
認知症とまぎらわしい病気
認知症と似た症状がある病気として、以下が挙げられます*11。
- 甲状腺機能低下症
- 肝性脳症(肝不全)
- 腎不全
- 呼吸不全
- ビタミン(B1、B12、葉酸等)欠乏
- 中毒(薬物、一酸化炭素、アルコール等)
など
これらの疾患は、血液検査や尿検査で診断されるものも多いため、気になる症状があればすみやかに医療施設を受診することが大切です。
認知症の初期症状対策家族はどうすればよい?
認知症を疑ったら、かかりつけ医や専門医に相談しよう
認知症を疑ったら、まずはかかりつけ医に相談しましょう。日頃から患者の状態を把握しているかかりつけ医であれば、これまでと比べて日常生活能力がどう変化しているかを評価しやすいためです。また、必要に応じて認知症専門の医療施設や専門機関を紹介してもらうことも可能です*12。なお、認知症の専門科は認知症外来やもの忘れ外来、脳神経内科、精神科、老年病科、脳神経外科などです。かかりつけ医がいない場合や受診先を迷う場合は、お住まいのエリアの「地域包括支援センター」に相談してみましょう。
認知症の診断に精通した専門医や“もの忘れ外来”を受診したい場合は、下記サイトから探せます*13,*14。
日本認知症学会 専門医・施設を検索(外部サイト)
認知症の人と家族の会 全国もの忘れ外来一覧(外部サイト)
本人に認知症の検査を受診してもらうためのコツ
家族が認知症疑いの本人に受診をすすめても、受診したがらないことも少なくありません。スムーズに受診へとつなげるための3つのコツを紹介します*15。本人の気持ちを尊重しながら適切な医療につなげるためにも、参考にしてみてください。
コツ1:「健康診断」や「脳ドック」をすすめる
心理的なハードルを下げるために、「健康診断」や「脳ドック」をすすめ、その延長として認知症の検査を受診してもらう方法です。なかでも脳ドックでは、認知症のリスクや兆候について調べることができる場合もあります。
コツ2:かかりつけ医から検査をすすめてもらう
かかりつけ医に相談し、認知症の専門医を紹介してもらいましょう。信頼関係のある医師からのすすめで、本人も受け入れやすくなります。
コツ3:地域包括支援センターに相談する
医療施設に抵抗がある場合は、地域包括支援センターに相談するのもひとつの手です。地域包括支援センターは、高齢者の生活全般に関する相談窓口であり、認知症疑いの方への家庭訪問や医療施設との連携、行政手続きのサポートなども行います。
脳ドックでは“認知症のリスク”を把握できる
脳ドックで認知症の早期発見に役立つ検査
脳ドックとは、脳に特化した検査を行う専門ドックです。脳ドックではおもに、脳血管疾患の代表例である「脳卒中」を発見する検査が行われますが、認知症にフォーカスしたプラン(コース)やオプション検査を用意している医療施設もあります。
脳ドックで認知症の早期発見に役立つ検査には、以下があります。
- 簡易的な認知機能テスト
- VSRAD®(MRIを使用して脳の萎縮度合いを調べる)
- MCIスクリーニング検査(血液検査でMCIのリスクを評価する)
- APOE遺伝子検査(血液検査でアルツハイマー型認知症に関連する遺伝子を調べる)
なお、これらは認知症のリスクを評価する検査であり、認知症の確定診断はできません。認知症検査の詳細や費用は、以下で詳しく解説しています。
VSRAD®の詳細や注意点は、以下の記事で詳しく解説しています。
家族に脳ドックギフト券をプレゼントする
両親やパートナーなど、認知症が疑わしい本人が受診したがらない場合は、相手を気遣う気持ちを込めて、脳ドックのギフト券をプレゼントするのも一案です。普段は医療施設に足が向きにくい方でも、「ギフト券があるなら受けてみようかな」と受診のハードルを下げるきっかけになることがあります。
「マーソギフト券」は、全国1,500以上の医療施設の豊富なプランの中から、自分にあったものを選択できます。詳細はこちらをご覧ください。
参考資料
*1.内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 知っておきたい認知症の基本
*2.国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 こころの情報サイト 認知症
*3.九州大学 「令和5年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業) 認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究 報告書」
*4.認知症介護研究・研修大府センター(厚生労働省老人保健健康増進等事業 改訂4版)「若年性認知症ハンドブック」2020年
*5.東京都健康長寿医療センター研究所 「若年性認知症の有病率・生活実態把握と多元的データ共有システム」2020年
*6.東京都福祉局 とうきょう認知症ナビ 認知症に早く気づくことが大事!
*7.国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」2022年
*8.日本神経学会「認知症診療ガイドライン2017」第4章
*9.認知症予防財団 認知症とは
*10.認知症の人と家族の会 家族がつくった 「認知症」早期発見のめやす
*11.長寿科学振興財団 健康長寿ネット 認知症
*12.国立精神・神経医療研究センター認知症・もの忘れ
*13.日本認知症学会 専門医・施設を検索
*14.認知症の人と家族の会 全国もの忘れ外来一覧
*15.認知症の人と家族の会 認知症に関する医学知識WEB版