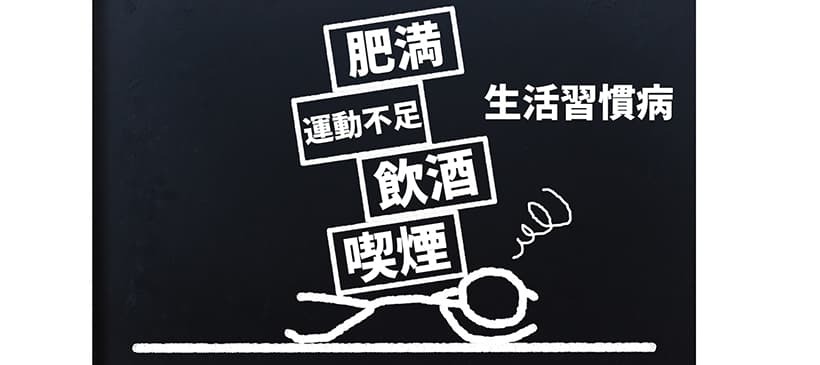全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)に加入している方の家族(被扶養者)は、特定健康診査(以下、特定健診)をおトクに受けることができます。特定健診とはメタボリックシンドロームの予防と改善を目的として国や保険者などが実施する健診のことで、メタボ健診と呼ばれることもあります。協会けんぽでは、加入者の健診を「生活習慣病予防健診」、家族(被扶養者)の健診を「特定健康診査(特定健診)」と区別しており、それぞれ検査内容や費用が異なります。
この記事では協会けんぽ家族向けの特定健診について詳しく解説します。簡単に検査内容をグレードアップできるおすすめのプランや、特定健診を受ける際に医療施設を選ぶポイントについてもあわせて解説しているので、40歳をむかえて協会けんぽの家族向け特定健診を利用しようと考えている方におすすめです。
★こんな人に読んでほしい!
・家族(扶養者)が協会けんぽに加入している40歳以上の方
・協会けんぽの特定健診を利用しておトクに健康診断を受けたい方
・自分に合う健診が受けられる医療施設の選び方を知りたい方
★この記事のポイント
・協会けんぽの特定健診の目的はメタボリックシンドロームの予防と改善。がん検診は含まれていない(がんの早期発見が目的ではない)
・特定健診の検査項目や費用は、協会けんぽ加入者向けプランと家族(被扶養者)向けプランでそれぞれ異なる
・協会けんぽの家族向け特定健診には2つのタイプがあり、集合Aタイプ(集団健診)と集合Bタイプ(個別に健診機関で受ける)のどちらを選択するかで費用が異なる
・特定健診プラスや人間ドックを利用すれば特定健診に含まれていていない検査項目を同時に受けることができる。また、自治体によってはがん検診と同時受診できる場合がある
目次
特定健診(特定健康診査)の目的はメタボリックシンドロームの予防と改善
特定健診の受診者は年々増加。メタボの高リスク群には専門家が保健指導を実施
特定健診の目的はメタボリックシンドロームなどの生活習慣病を予防、改善することです。注意したいこととして、がん検診ではないため基本的にがんを早期発見するための検査内容にはなっていません。生活習慣を早期に改善することで高血圧の改善、脂質異常症の減少、糖尿病患者の増加を抑制し、結果として脳梗塞や脳出血、心筋梗塞など死に到る病気の発生率を下げることを目指しています。
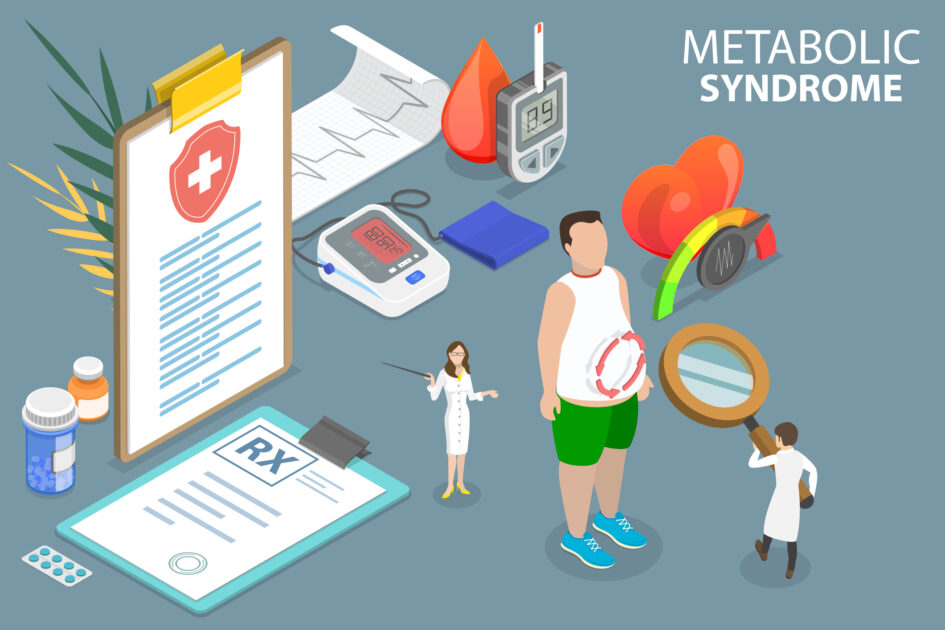
2008年(平成20年)4月1日以降、高齢者医療確保法に基づいて、医療保険者(健診の対象となる方が加入している国民健康保険もしくは被用者保険)は特定健診ならびに特定保健指導を実施することが義務化されました*1。特定保健指導とは、生活習慣病の発症リスクが高いと判断された方のみが受けることができる保健指導のことで、血糖値や血圧、生活習慣(運動、食事、喫煙)などを考慮して対象者が決定します。特定健診の受診者は年々増加傾向で、2019年度には全国でおよそ2994万人が特定健診を受診しました*2。
先ほどお伝えした通り、特定健診はメタボリックシンドロームに特化した検査内容になっているため、一般的な健康診断とも検査内容が異なります。具体的な相違点はおもに以下の通りです*3。
- 特定健診には視力、聴力の測定、胸部X線検査と喀痰検査が含まれていない
- 特定健診では医師が必要と判断した場合、眼底検査を受けることができる
- 動脈硬化に大きく関係しているLDL(悪玉)コレステロールや、貧血に関係しているヘマトクリット値を含む血液検査が必須項目となっている
協会けんぽ特定健診は40歳から74歳の被扶養者(家族)が対象
協会けんぽが実施している特定健診は、加入者向けと加入者の家族(被扶養者)向けでそれぞれ名称が異なるのが大きな特徴です。前者は「生活習慣病予防健診」、後者は「特定健診」と呼ばれそれぞれ対象年齢や検査内容、検査費用などが異なります。それぞれの特徴は下記の表の通りです*4,*5。検査費用については次の項でくわしく説明します。
| 健診の名称 | 生活習慣病予防健診 | 特定健診 |
| 対象者 | 協会けんぽ加入者 | 加入者の家族(被扶養者) |
| 対象年齢 | 35歳以上75歳未満※ ※下記の方も対象内 ・受診日前日までに75歳の誕生日を迎える方 ・受診する年度内に35歳を迎える方 | 40歳以上75歳未満※ ※下記の方も対象内 ・受診日前日までに75歳の誕生日を迎える方 ・受診する年度内に40歳を迎える方 |
| 検査項目 | 【一般健診】 ・診察等 ・問診 ・身体計測 ・血圧測定 ・尿検査 ・血液検査(ヘマトクリット値、血色素測定、赤血球数白血球数) ・心電図検査 ・眼底検査※ ・便潜血検査 ・胸部レントゲン検査 ・胃部レントゲン検査 ※医師の判断により一部の方のみ実施 | 【基本的な健診】 ・診察等 ・問診 ・身体計測 ・血圧測定 ・尿検査 ・血液検査(血中脂質検査 、肝機能検査 、血糖検査 ) 【詳細な健診※】 ・心電図検査 ・眼底検査 ・よりくわしい血液検査(貧血検査 、血清クレアチニン検査) ※医師の判断により一部の方のみ実施 |
協会けんぽ特定健診の費用

協会けんぽの家族向け特定健診には2つのタイプがあり、集合Aタイプ(集団健診)と集合Bタイプ(個別に健診機関で受ける)のどちらを選択するかで費用が異なります。それぞれの費用と特徴は下記の表の通りです。
| 集合Aタイプ | 集合Bタイプ | |
| 費用(自己負担額) | 無料(全国一律) | 3000〜5000円程度 |
| 受診できる医療機関の数 | 都内約220施設 | 各地区の医師会と連携している医療施設で受診することができる(医師会と協会けんぽが契約をしている場合に限る) |
| メリット | 受診費がかからない | ・受診できる医療施設の数が多い ・自分の都合にあわせて受診を予約しやすい |
| デメリット | 実施会場や受診できる日時に制限が多い | ・受診費がかかる ・地区によって費用、受診可能期間が異なる |
協会けんぽ加入者のご家族(被扶養者)は、年度内1回に限り、協会けんぽから健診費用の一部補助を受けることができるため、上記の通りおトクに特定健診を受けることが可能です。補助額は基本的な健診であれば上限7150円、医師の判断でさらに詳細な健診を受診した場合にはさらに3400円の補助を受けることができ、自己負担額はこの補助額を差し引いた額になります*5。なお、健診費用が補助費用を下回った場合、自己負担はありません。
特定健診の検査内容とそれぞれの検査でわかること
特定健診の検査項目は「基本的な健診」と「詳細な健診(医師の判断で一部の方のみ実施)」に分かれており、いずれも高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病を見つけるのに特化した検査内容となっています。この項では特定検診の検査内容についてくわしく解説します。
基本的な健診
診察(問診、視診、触診、聴打診など)
【検査内容】
現在の健康状態を医師が問診、視診、触診、聴打診などで確認します。服薬歴や喫煙歴について答えるほか、既往歴、貧血や体重変化、運動習慣、食習慣について気になることがあれば医師に伝えることが可能です。診察と検査の結果を踏まえて、医師がさらに検査が必要だと判断した一部の方は、詳細な健診を追加で受ける必要があります。
【検査からわかること】
生活習慣病の発症リスクを高める生活習慣の有無がわかります。
身体計測
【検査内容】
身長、体重、腹囲を計測し、肥満度の指標であるBMI(Body Max Index)を算出します。
【検査からわかること】
BMIをもとにして肥満や低体重(やせ)を判定し、メタボリックシンドローム予備軍かどうかを簡易的に評価します。BMIが22になるときの体重が標準体重で、もっとも病気になりにくい状態であるとされています。日本肥満学会の基準ではBMI25以上が肥満とされ、この基準を超えると脂質異常症や糖尿病、高血圧などの生活習慣病の発症リスクが2倍以上になることがわかっています*6。
血圧測定
【検査内容】
血圧(心臓から送り出された血流が血管の内壁を押す力)を測定します。
【検査からわかること】
高血圧の有無を調べて、心臓のポンプ機能に明らかな異常がないかどうか、また動脈が硬くなっていないかどうかを簡易的に評価します。具体的に高血圧とは、140mmHg/ 90mmHg以上の場合を指します*7。高血圧が慢性化すると動脈硬化が進行して脳卒中、心筋梗塞、心不全、腎臓病といった重篤な病気を引き起こすことがわかっています。
血液検査(脂質検査、糖質検査、肝機能検査)
【検査内容】
採血を行い、メタボリックシンドロームなどの生活習慣病に関わる項目を測定します。
【検査からわかること】
・脂質検査
血液中の中性脂肪、HDL(善玉)コレステロール、LDL(悪玉)コレステロールなどを測定します。基準値を超える場合には脂質異常症(高脂血症)や動脈硬化の疑いがあります。
・糖質検査
空腹時の血糖値や糖尿病に関わるHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)という値を測定します。HbA1cは過去2ヶ月程度の血糖値の平均を表しており、いずれも基準値を超えると糖尿病の疑いがあります。
・肝機能検査
肝臓の働きを示すAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)といった値を測定します。脂肪肝、アルコール性肝炎、ウイルス性肝炎の疑いなどを調べることができます。
尿検査
【検査内容】
尿を採取し、腎臓、尿路の状態や糖尿病の発症リスクなどを反映する項目(尿糖、尿蛋白)を測定します。
【検査からわかること】
・尿糖
尿中の糖分の量を示しています。陽性の場合、腎機能の低下や糖尿病の疑いがあります。
・尿蛋白
尿中のタンパク質の量を示しています。陽性の場合、糖尿病や甲状腺機能の異常などの疑いがあります。
詳細な健診(医師の判断で一部の方のみ実施)
ここまでお伝えした検査内容に加えて、医師が診察をして必要だと判断した場合には心電図検査、眼底検査、貧血検査、血清クレアチニン検査といったよりくわしい検査が実施されます。そのため、すべての方が受けられるわけではありません。この項では詳細な健診の検査項目についてご説明します。
心電図検査
【検査内容】
ベッドに仰向けに寝て、手首、足首、胸などに電極を貼り付けて行う検査です。心臓のリズムや動きが正常かどうかを簡易的に評価します。
【検査からわかること】
心臓のリズムが乱れる不整脈や、心臓の血管が狭くなるなど心臓に十分な血液が供給されていないことによって起こる狭心症の有無がわかります。不整脈や狭心症は突然死の原因のひとつである心筋梗塞を引き起こす場合もあります。
眼底検査
【検査内容】
眼底カメラなどの器具を用いて眼の奥にある血管、視神経、網膜の状態を評価する検査です。
【検査からわかること】
おもに糖尿病性網膜症、すなわち糖尿病によって視力が低下する病気の疑いを調べることができます。糖尿病性網膜症は失明につながる病気ですが、かなり進行してもほとんど自覚症状がありません*8。急激な視力低下などの自覚症状が現れてからでは治療が難しいこともあるため早期発見が重要です。
貧血検査
【検査内容】
採血を行い、貧血に関わる項目(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)を測定します。ヘマトクリット値とは、血液中に含まれる赤血球の体積の割合を表す値です。赤血球数、血色素量(ヘモグロビン濃度)、ヘマトクリット値と臨床症状などを組みあわせて赤血球の中に含まれるヘモグロビンの量に異常がないかどうかを判定します。
【検査からわかること】
貧血の疑いがあるかどうかを調べることができます。赤血球中に含まれているヘモグロビンには全身へ酸素を運ぶ役割があるため、ヘモグロビンが少なくなっている(ヘマトクリット値が下がっている)状態だと貧血の可能性があります。貧血の原因はさまざまで栄養不足、月経のほかに、腎臓や骨髄の異常などの可能性があります。反対にヘモグロビンが多すぎる(ヘマトクリット値が上がっている)状態でも脱水、多血症、骨髄の異常などの可能性があります。
血清クレアチニン検査
【検査内容】
採血を行い、血液中のクレアチニン(血清クレアチニン)の量を測定します。血清クレアニチンと年齢および性別から推算糸球体ろ過量(eGFR)を計算し、腎機能の状態を評価します。
【検査からわかること】
クレアチニンは筋肉で作られるアミノ酸の一種です。クレアチニンは老廃物として腎臓でろ過される物質であるため、腎臓が正しく機能していれば血液中には増えていきません。おもに腎臓の機能が正常かどうか、もしくは腎臓の病気(急性腎炎、慢性腎炎、腎不全、腎盂腎炎、尿管結石)があるかどうかを簡易的に評価することができます。なお、クレアチニンは筋肉量の違いでも変化するため男性と女性で基準値が異なります。
上記のように、協会けんぽの加入者の家族は特定健診を利用してメタボリックシンドロームなどの生活習慣病に特化した検査をおトクに受けることができます。とくに専業主婦の方やパート、アルバイトなどで健康診断を受ける機会がない女性は積極的に利用することをおすすめします。
しかし、デメリットとして加入者本人の生活習慣病予防健診にくらべると検査項目が少なかったり、がん検診の検査は含まれていなかったりといった制限もあります。ご自身にあった検査を追加したい方はこれからご紹介する「特定健診プラス」や人間ドックの利用を検討してみてください。
追加プランや人間ドックなどを利用すれば検査項目を増やすことが可能
生活習慣病予防健診と同等の検査を受けるなら「特定健診プラス」が便利

特定健診プラスとは、協会けんぽが提供している検診プランのことです。協会けんぽ加入者の家族が生活習慣病予防健診と同等レベルの検査内容を受けることができます。受診する医療機関に直接電話するだけで手軽に申し込みができるため、「特定健康診査だけでは検査項目が少ない」「がんの検診も同時に受診したい」「夫婦で一緒に受診したい」という方におすすめです。具体的には、特定健診の検査項目に以下の生活習慣病予防健診項目が追加されます。
- 胸部レントゲン検査
- 胃部レントゲン検査(バリウム検査)
- 便潜血検査
- 心電図検査
- 視力聴力検査
- 血液一般検査
- 尿検査(潜血)
- 血中脂質検査(総コレステロール)
- 肝機能検査(ALP)
- 腎機能検査
プランの費用は、これらの検査をすべて受けて自己負担額は最高1万1715円(東京都の場合)です*9。生活習慣病予防健診の項目に対する協会けんぽからの費用補助はありませんが、特定健診の項目に対しては一部補助を受けることができるため、全額自己負担で検査を受ける場合に比べて1万円以上おトクに受けることができます。特定健診プラスはすべての医療機関で実施されているわけではありません。特定健診プラスを利用できる医療施設の一覧は協会けんぽのWebサイトから確認することができます。なお、追加される検査項目やプランの詳細は医療機関によって異なります。
市区町村によっては自治体のがん検診と同時受診できる場合がある
協会けんぽの特定健診には、がん検診は含まれていません。ただし、市区町村によっては協会けんぽの特定健診と自治体のがん検診を同時に受けられる場合があります。なお2021年6月現在、国が自治体のがん検診の項目として定めている内容は以下の通りです*10。がん検診の内容は自治体ごとに異なる場合があるため、詳細は自治体のWebサイトをご確認ください。
| がん検診の種類 | 検診方法 | 対象年齢 | 検診間隔 |
| 胃がん検診 | 問診、バリウム検査(胃X線検査)または胃カメラ(胃内視鏡検査) | 50歳以上※バリウム検査は40歳以上に対して実施可 | 2年に1回※バリウム検査は毎年実施可 |
| 大腸がん検診 | 問診、便潜血検査 | 40歳以上 | 毎年 |
| 肺がん検診 | 問診、胸部X線検査、喀痰細胞診(対象者のみ) | 40歳以上 | 毎年 |
| 乳がん検診 | 問診およびマンモグラフィ(乳房X線検査) | 40歳以上 | 2年に1回 |
| 子宮頸がん検診 | 問診、視診、子宮頸部細胞診、内診必要に応じてコルポスコープ検査 | 20歳以上 | 2年に1回 |
自治体のがん検診の最大のメリットは費用が安価であることです。これは、自治体が検査費用のほとんどを公費で負担してくれるからです。そのため協会けんぽの特定健診と自治体のがん検診を同時に受けられる方は積極的に利用することをおすすめします。
同時受診の申し込み方法は自治体によって異なります。医療機関と自治体それぞれに「協会けんぽ加入者で特定健診(または、がん検診)を受けたい」という旨を連絡する必要がある場合もあります。まずは、自治体のがん検診との同時受診ができるかどうかをお住まいの地区の協会けんぽのWebサイトまたは自治体に確認しましょう。
自分にあった検査を選びたい方は人間ドックがおすすめ
生活習慣病予防健診の項目に含まれていない検査を受けたい方や、がん検診の対象年齢に満たないけれど検査を受けたい方には人間ドックがおすすめです。人間ドックでは協会けんぽの加入者とその家族(被扶養者)が利用できるおトクなプランが用意されている場合があります。プランの内容と費用は医療施設によって異なります。人間ドックは全額自己負担のためやや高額になりますが、協会けんぽのご家族であれば特定健診の項目に対する費用補助を差し引いた金額で利用できるため比較的おトクです。
特定健診の受診でおすすめの医療施設の選び方5つ
協会けんぽの特定健診を実施しているかどうか
まずは、協会けんぽ加入者の家族(被扶養者)が利用できる特定健診を実施しているか医療施設かどうかを確認しましょう。協会けんぽと提携している医療施設のなかには生活習慣病予防健診は実施しているけれど、家族向けの特定健診には対応していない場合などもあります。
次に、特定健診のAタイプ(集団健診)とBタイプ(個人健診)の両方に対応しているのか、どちらか一方だけに対応しているのかを確認しておきましょう。Aタイプの場合は受診費がかからない点がメリットですが、受診できる医療機関の数が限られています。一方で、Bタイプは受診費がかかりますが、協会けんぽと各地区の自治体が契約を結んでいるため受診できる医療機関の数が多い点や、個人受診であるためご自身の都合に合わせて受診しやすい点がメリットです。受診する医療施設がAタイプとBタイプのどちらに対応しているかどうかは各地区の協会けんぽのWebサイトから確認することができます。
特定保健指導を受けられるかどうか
特定保健指導とは、特定健診の結果から生活習慣病の発症リスクが高いと判断された方のみが受けることができる保健指導のことです。メタボリックシンドロームの発症リスクに応じて、動機付け支援と積極的支援の2タイプがあります。
医師、看護師、管理栄養士、保健師などが専門的な知識に基づいて生活習慣を改善していくサポートをしてくれるため、自分だけでは前向きに生活習慣の改善をするのが難しい方にとくにおすすめしたい制度です。特定保健指導の対象となった場合には自宅に特定保健指導利用券が郵送されて、希望する医療施設を受診することになるのが一般的ですが、医療施設によっては特定健診当日に特定保健指導を利用できる場合があります。
すべての医療施設で特定保健指導を受けられるわけではないため、特定保健指導を受けたいと考えている方は事前に医療施設に問い合わせてみることをおすすめします。なお、特定保健指導を受けられる医療施設の一覧は協会けんぽのWebサイトからも確認することができます。
特定保健指導の費用は、協会けんぽの加入者とそのご家族(被扶養者)で異なります。加入者本人の場合は協会けんぽが全額費用を補助してくれるため原則無料です。家族が特定保健指導を受ける場合にも協会けんぽから補助はありますが、補助額を超える費用については自己負担になります。特定保健指導の費用は医療機関によって異なるため、具体的な費用が知りたい方は医療機関に直接問い合わせをしてみてください。
土日や午後などの受けたい時間に対応しているか
平日や日中に時間がとりにくい方でも、協会けんぽの特定健診は受診が可能です。例えば早朝や夕方、土日祝日でも特定健診を受診できる医療施設もあります。どうしても都合のよいプランがない場合は、検査内容によっては時間を調整してもらえることもあるので、医療施設に問い合わせてみるのもよいかもしれません。
通常、午前中に特定健診を受ける場合には前日の夕食以降は絶食で、水やお茶以外は飲まないのが望ましいとされています。これは採血で空腹時の血糖などを測定するためです。午後や夕方に特定健診を受ける場合には、当日の朝食を軽めに済ませてそれ以降は絶食で水やお茶以外は飲まないようにしましょう。
忙しい方ほど「面倒だな」とあと回しにしてしまいがちなので、まずは細かいプランを比較せずにご自身のスケジュールに合う人間ドック施設を探してみてください。
受けたい検査項目に対応しているかどうか
特定健診の検査項目はすでにお話しした通りですが、医療施設によっては対応していない検査項目もがあります。例えば、眼底検査(医師が必要と判断した一部の方のみ実施)は、眼底カメラなど専用の器具で眼内を撮影する検査ですが、眼底カメラを設置していない医療施設では検査を受けることができません。その場合はほかの医療施設に紹介受診することになります。
また、特定健診に含まれていない検査項目を組み合わせたい方は、受けたい検査プランに対応している医療施設かどうかも事前に確認しておきましょう。特定検診プラスやがん検診(胃カメラやマンモグラフィ、便潜血検査など)などはすべての医療施設で受けられるわけではありません。各医療施設が対応している特定健診の検査項目は協会けんぽのWebサイトで確認することができます。不明な点がある場合には受診したい医療施設に直接問い合わせてみることをおすすめします。
女性に配慮した施設かどうか
健診は検査着に着替えて移動をする場合があるため、女性のなかには男性と一緒に健診を受けることに抵抗を感じる方もいると思います。近年は女性に配慮した医療施設が増えてきており、女性専用の待合室が用意されていたり、レディースデーが設けられていたりするなどさまざまな取り組みがされています。
上記のほかにも、女性に配慮した取り組みの例としては以下のような項目が例に挙げられます。
- すべて女性の医師や技師、スタッフが対応している
- キッズルームや託児所がある
- パウダールーム完備
検査への不安がある方や、恥ずかしさが気になって検査をためらっている方は上記のような女性に配慮した取り組みをしている医療施設を選ぶと安心して受診することができるのでおすすめです。なお、託児所の利用には事前予約が必要な場合があるため、医療施設へ問い合わせをしてみてください。
参考資料
*1. 厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム(平成 30 年度版)」(2018年4月)
*2. 厚生労働省「2019年度 特定健康診査・特定保健指導の 実施状況について【概要】」
*3. 厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の円滑な 実施に向けた手引き(第 3.2 版)」(2021年2月)p.6
*4. 協会けんぽ「令和3年度(2021年4月~2022年3月) 生活習慣病予防健診のご案内」
*5. 協会けんぽ「令和3年度(2021年4月~2022年3月) 特定健診(特定健康診査)のご案内」
*6. 厚生労働省「e-ヘルスネット」BMI
*7. 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」p.18
*8. 日本糖尿病眼学会「糖尿病網膜症診療ガイドライン(第 1 版)」2020年12月
*9. 協会けんぽ「『特定健診プラス』のご案内」
*10. 厚生労働省「市区町村のがん検診の項目について」