日本人女性の9人に1人は生涯で乳がんになると推定されています*1。女性がかかるがんの中ではもっとも多く、若い年齢で乳がんにかかる率も年々上昇しています*2。
原則40歳以上であれば自治体の乳がん検診を受けられますが、自治体によっては検査内容がマンモグラフィに限られていることがあり、乳腺エコー検査(乳腺超音波検査)などを追加したい場合には自費で受ける場合が多いです。
この記事では乳がん検診の3つの受診方法と、それぞれの費用相場を中心に解説します。40歳未満の受診は自費にはなりますが、受診する有用性や年齢に合わせた検査の選び方についてもご紹介します。
★こんな人に読んでほしい!
・40歳未満で乳がん検診に興味はあるが、費用が高額になるのではないかと心配して受診を決めかねている女性
・40歳以上で乳がん検診の費用相場を把握したい女性
★この記事のポイント
・乳がんは女性の部位別がん罹患率でトップ。40代前後から増え始めるが、30代前後の若い世代でも乳がんによる死亡数が増えている
・自治体の乳がん検診は、原則40歳以上の女性を対象に2年に1回、マンモグラフィと問診を受けることが国から推奨されている
・乳がん検診を受ける方法はおもに3つあり、自治体による検診、企業検診、全額自己負担での検診(自由診療)に分けられる
・乳がん検診の費用相場(自由診療の場合)はマンモグラフィが4000〜8000円、乳腺エコー検査が3000円〜6000円程度
・血縁者に乳がんや卵巣がんになっている人がいる場合は遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)の可能性があるため、40歳を待たずに検診を受けたほうがよい
・乳がん検診の検査は40歳以上ならマンモグラフィが第一選択。乳腺エコー検査を併用するとさらによい。40歳未満なら乳腺エコー検査単独もしくは乳腺エコー検査とマンモグラフィの併用がおすすめ
目次
乳がんは女性の罹患率トップ。検診での早期発見・早期治療が大切
乳がんの発症リスクは30代後半から急速に高まる
乳がんは日本人女性がもっともかかりやすいがんです。30代後半から乳がんによる死亡数は急速に高まり、30歳から69歳までは乳がんが女性の死因第1位です*3。仕事や子育てに励む働き盛りの女性こそ、乳がんに気をつける必要があります。乳がんは早期発見して適切な治療を行えば5年相対生存率が9割と予後もよいです*4。乳がんで亡くなる可能性を下げるために、定期的に乳がん検診を受けましょう。
自治体の乳がん検診は原則40歳以上が対象
厚生労働省が定めた乳がん検診の指針に基づいて、自治体では乳がん検診が実施されています。対象は40歳以上の女性、頻度は2年に1度、検査内容は問診とマンモグラフィが基本です。40歳未満の女性がマンモグラフィや乳腺エコー検査(乳腺超音波検査)を受けた場合、死亡率が低下するという明らかな検証結果はまだ得られていませんが、自治体によっては、30歳代の女性を対象に乳腺エコー検査(乳腺超音波検査)を実施しているところも増えてきています。受診方法は、集団検診と個人検診の2パターンがあり、集団検診は会場になる自治体の施設などで指定された日に受診、個人検診の場合は自治体が指定した医療機関に自身で予約をして受診します。
費用は、自治体が一部を公費負担するため、自己負担は比較的安価です。また、多くの自治体では、特定年齢(当該年度に41歳になる場合など)に無料で受診できます。船橋市を例に挙げると、30歳代と40歳以上のいずれも500円の自己負担額で受けることができます*5。自治体ごとに年齢や受診時期、検査内容が設定されているため、自治体Webサイトで確認してみてください。
乳がん検診の費用は受診方法によって異なる
乳がん検診の受診方法
乳がん検診を受ける方法は大きく分けて次の3つに分けられます。
1)自治体の乳がん検診で受ける
2)健康組合や職場での健康診断で受ける
3)全額自己負担で受ける(自由診療)
自治体の乳がん検診については前項でお話ししたので、この項では2)企業健診と3)自費での受診方法について解説します。
【健康組合や職場での健康診断で乳がん検診を受ける】
会社員の女性は、事業者検診(企業が独自に実施する健診)や協会けんぽの特定健康診査(特定健診)などで乳がん検診を受けられる可能性があります。
自治体の検診と同様に、対象年齢や検査内容に条件があるため、勤めている会社の乳がん検診への取り組みをまずは調べてみてください。
トヨタ自動車を例に挙げると、20歳以上の女性を対象に年に1回、乳がん検診か子宮検診(子宮頸がん検診)をいずれも1000円の負担額で、契約する医療機関もしくは巡回バスで実施しています。乳がん検診の場合、40歳未満は乳腺エコー検査のみ、40歳以上は乳腺エコー検査かマンモグラフィのどちらかを選択することが可能です*6。
また専業主婦の女性も、夫が会社員の場合は、被扶養者として乳がん検診をおトクに受けられる可能性があります。
【全額自己負担で乳がん検診を受ける(自由診療)】
自治体の検診や企業検診を利用できない方で、「症状はないけれど乳がんの検査を受けたい」という場合は、医療施設が独自で実施している乳がんの検査を全額自己負担で受けることができます。費用が高いというデメリットはありますが、対象年齢や検診頻度などの制限がなく、検査方法を選べることがメリットです。乳がんの検査を行っている医療施設や人間ドックに直接予約をするだけでOKです。
自費で受けるメリットとしては以下のことが挙げられます。
- 40歳未満の女性も受けることができる
- 自身のスケジュールに合わせて予約できる(自治体や企業の乳がん検診は受診期間が設定されているため)
- 自分にあった医療施設で受けることができる(女性専用のクリニックなど)
- 自治体や企業の乳がん検診に含まれていない検査も受けることができる
自治体の乳がん検診には乳腺エコー検査(乳腺超音波検査)が含まれていないことが多いため、乳腺エコー検査を受けたい場合は自費での受診になります。また、3Dマンモグラフィ(トモシンセシス)や乳房専用PEM装置といった最新機器やMRI装置を利用した検査は一部の医療施設にしか導入されていません。自治体から指定されていないこのような医療施設で検査を受けたい場合も、自費であれば受けることができます。
また、乳がん以外の病気(子宮頸がん、卵巣がん、糖尿病、不整脈など)も心配な方は、レディースドックを利用するという方法もあります。
ただし、「しこりが触れる」「乳頭から分泌物がある」など乳がんを疑う症状がある場合には乳がん検診ではなく、診察を受けてください。医師が症状を認めた場合には、保険診療が適用されます。
乳がん検診の費用相場
【自治体のがん検診の場合(自己負担額)】
| 検査名 | 費用 |
| マンモグラフィ | 無料〜2000円前後 |
| 乳腺エコー検査 | 無料〜2000円前後 |
【自由診療の場合】
| 検査名 | 費用 |
| マンモグラフィ | 4000円〜8000円 |
| 乳腺エコー検査 | 3000円〜6000円 |
| 上記の両方を受ける場合 | 7000〜1万2000円 |
【保険診療で3割負担の場合(初診料・再診料除く)】
| 検査名 | 費用 |
| マンモグラフィ | 1000円〜3000円 |
| 乳腺エコー検査 | 1000円〜2000円 |
| 上記の両方を受ける場合 | 2000〜4000円 |
20代や30代でも乳がん検診を定期的に受けるのは有効
乳がんの発症リスクが高い人の特徴
乳がんの発症リスクは一般的に40歳前後から高まりますが、以下の項目に当てはまる方は、より高いリスクを持っていることが明らかになっています。
【乳がんの発症リスク因子】
- 高齢初産もしくは未出産
- 初潮が早く、閉経が遅い
- 閉経後、肥満になっている
- 血縁者が乳がんになっている
- 良性の乳腺疾患になったことがある
- 閉経後ホルモン補充療法・ピル(経口避妊薬)を服用した経験がある
親、子、姉妹に乳がんになった人がいる場合には、いない方に比べて乳がんの発症リスクが2倍以上になるということがわかっています*7。とくに、50歳以下の若い年代で乳がんや卵巣がんになった血縁者が複数いる場合には「遺伝性乳がん卵巣がん症候群」という遺伝子異常の可能性もあるため注意が必要です。

遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)とは
遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC:Hereditary Breast and Ovarian Cancer syndrome)とは、生まれつき「BRCA1」あるいは「BRCA2」という遺伝子に病的な変化を持っており、それによって特定のがんになりやすい体質のことを指します。2013年にハリウッド女優のアンジェリーナ・ジョリーさんがHBOCであることを公表し、予防的に両側乳房を切除したことでも話題になりました。
具体的には、乳がん、卵巣がん、前立腺がん、膵臓がんなどの発症リスクが通常よりも高いです。がんに発症にしてない方も含めて、200人〜500人に1人がHBOCに該当するといわれています*8。
HBOCの場合、25歳頃から徐々に乳がんの発症リスクが高くなるため、若いうちからこまめに検診を受診することが推奨されています。日本人に合わせた検診方法はまだ確立されていない状況ですが、アメリカのガイドラインでは25歳から年に1回の乳房MRI検査(MRIが利用できない場合にはマンモグラフィや乳腺エコー検査)を受けることが推奨されています。
ただし、乳房MRI検査による早期発見が死亡率を減少させるかどうかはまだ明らかではないこと、マンモグラフィによる被爆の影響があることなどから、HBOCの疑いがある方は乳腺専門の医師に相談をして自分にあった方法で若いうちから乳がん検診を受けることをおすすめします。
乳がんに現れやすい初期症状-自覚がなくてもがん検診の受診が大切
乳がんは進行とともに以下の症状が現れることがあります。
- 乳房にしこりがある
- 乳房にくぼんでいる部分やただれている部分がある
- 乳頭から血が混ざった分泌物がある
- 乳頭に陥没や変形がある
- 左右の乳房の形が非対称である
- 脇の下が腫れて違和感がある
上記のような症状を自覚している場合には、乳がん検診を待たずに診察を受けてください。また、自覚症状がない方も、乳がんは早期だと変化が現れにくいため、定期的に検診で確認をするようにしましょう。
乳がん検診の検査方法-発見率を高めるならマンモグラフィとエコーを併用したほうがよい
検査の種類と年代別の選び方
乳がん検診の検査はおもに3つあり、マンモグラフィ、乳腺エコー検査(乳腺超音波検査)、視触診に分けられます。この項ではマンモグラフィと乳腺エコー検査の特徴と年齢別の選び方について解説します。
【乳がん検診のおもな検査】
・マンモグラフィ
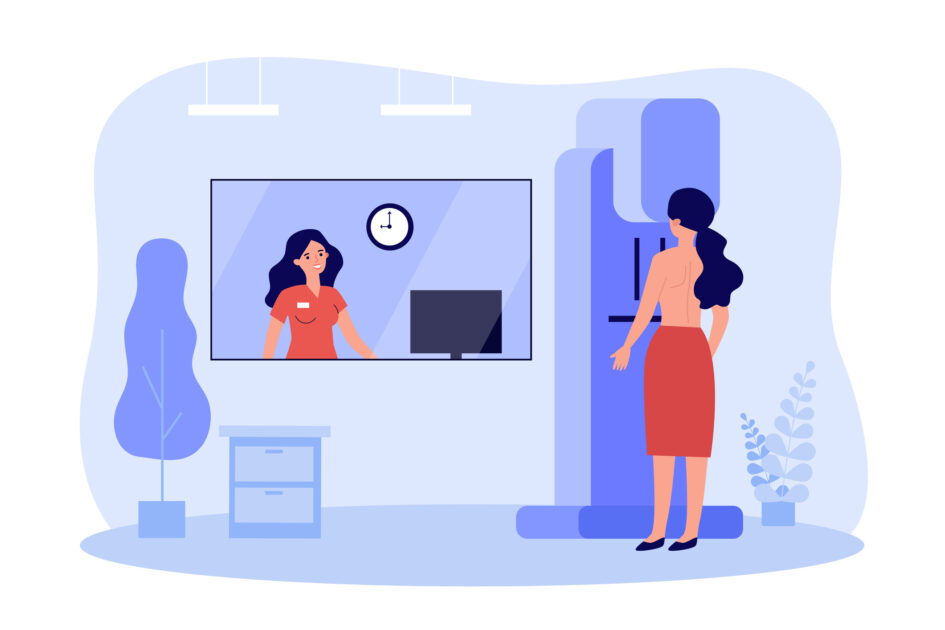
X線を利用して乳房の画像を撮影します。乳がんの死亡率を減少させる科学的な根拠が認められている唯一の検査です。乳房をアクリル板で挟んで薄く広げて、乳腺内を見やすくしてから撮影をします。20〜30代など乳腺組織が発達している若い方に多い「高濃度乳腺」の場合には、がんと乳腺を画像上で区別するのが難しくなるため、一般的に40代以上を対象にしています。検査時間は10〜15分前後です。
マンモグラフィは石灰化をともなう乳がんや、比較的硬さがあるしこりを見つけるのに優れた検査です。石灰化の形状や個数や石灰化の広がり方、しこりの形状などを診て、悪性を疑ったほうがよいかを判定しています。微小石灰化は乳房内にできたとしてもほぼ無症状のため、マンモグラフィを受けることで超早期にがんを発見できる確率が高くなります。
・乳腺エコー検査(乳腺超音波検査)
乳腺エコー検査はベッドに仰向けに寝た状態で乳房の上にゼリーを塗って超音波を当てることで乳房の画像を得る検査です。マンモグラフィと異なり、検査にともなう被爆や痛みがないため誰でも安心して受けられるというメリットがあります。検査時間は10分前後です。
乳腺エコー検査は、マンモグラフィには映りにくいしこりや、サイズが小さいしこりを見つけるのに優れていますが、石灰化を見つけるのには向いていません。検診において死亡率を減少させる効果はまだ検証中ですが、乳腺エコー検査のメリットを考慮して40歳未満の女性や40歳以上の高濃度乳腺の方を対象に実施している医療施設が多いです。マンモグラフィと併用することで乳がんを発見できる確率が上がります。
【年代別・検査の選び方】
年代別におすすめする乳がん検診の検査は以下の通りです。
- 20代〜30代前半の方:乳腺エコー検査
- 30代後半の方:乳腺エコー検査(マンモグラフィを併用してもよい)
- 40代以上の方:マンモグラフィ(高濃度乳腺の方は乳腺エコー検査を併用するのがおすすめ)
すべての方に当てはまるわけではありませんが、20〜30代の乳腺密度が高い方をマンモグラフィで撮影すると、乳腺の白っぽい濃度が目立ってしまい内部のしこりが見つけにくい傾向があります。多くはありませんが被爆の影響も受けるため、30代までの方は乳腺エコー検査を優先的に受けることをおすすめします。
乳がんの発症リスクが心配な方は、マンモグラフィと乳腺エコー検査を併用して受けるとよいです。栃木県の統計データによると、マンモグラフィと乳腺エコー検査をそれぞれ単独で実施した場合のがん発見精度は62%と54%でしたが、2つの検査を組み合わせた場合には85%まで上がったという結果が得られています*9。
検査ごとの注意点
マンモグラフィは被爆をする検査なので、以下の方は受けることができません。
- 妊娠をしているもしくは妊娠の可能性がある方
- 豊胸術などで乳房内に人工物が入っている方
- ペースメーカーが挿入されている方(乳房の一部であれば撮影できる場合もある)
- VPシャント、ポートなどを装着されている方
その他、車椅子などで撮影の体勢を保持するのが難しい場合には検査を受けられないことがあります。
マンモグラフィ検査時の痛みをできるだけ減らす工夫としては「胸が張りにくい生理開始後2、3日〜1週間の時期に受けること」「検査時に腕に力を入れすぎないこと」を心がけてみてください。マンモグラフィを受けたときの痛みの感じ方は個人差が大きいため、他人の感想は参考になりにくいです。また、年齢が上がるにつれて、乳腺が脂肪に置き換わっていくため、痛みは少なくなる傾向があります。
参考資料
*1. 国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」最新がん統計
*2. 日本乳癌学会「乳癌診療ガイドライン(2018年版 )」総説1 日本人女性の乳癌罹患率,乳癌死亡率の推移
*3. 日本対がん協会「もっと知りたい乳がん」2020年2月
*4. 国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」がん診療連携拠点病院等院内がん登録生存率集計(2010-2011年)
*5. 船橋市 各種がん検診・健康診査等のご案内 乳がん検診
*6. トヨタ自動車健康保険組合 女性のがん検診
*7. 日本乳癌学会「患者さんのための乳癌診療ガイドライン2019年版」Q4.乳がんと遺伝について
*8. 日本HBOCコンソーシアム HBOCとは
*9. 国立がん研究センター「有効性評価に基づく乳がん検診ガイドライン 2013年度版」2014年3月








