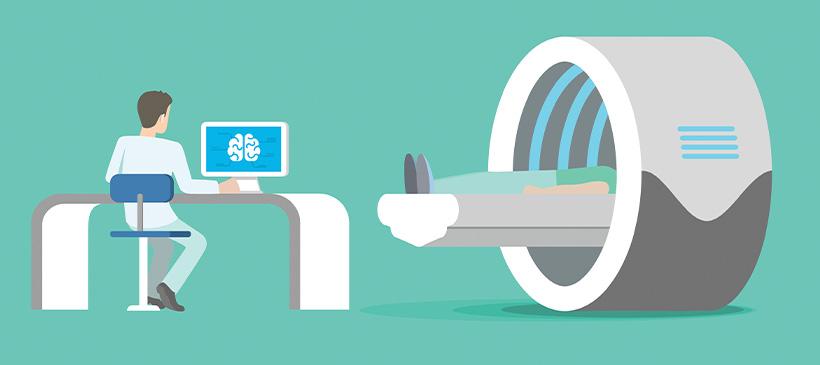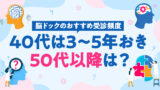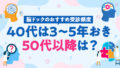脳ドックは、脳を専門的に検査し、おもに脳卒中を始めとする脳血管疾患のリスクの早期発見を目的としています。ここでは脳ドックの所要時間や検査の流れといった基本情報から、受診時の注意事項、閉所が苦手な方向けのMRI対処法まで紹介します。
★こんな人に読んでほしい!
・脳ドックにかかる時間や検査の流れを知りたい方
・脳ドックを受ける前に注意点を知っておきたい方
・脳ドックを受けたいが閉所が苦手な方
★この記事のポイント
・脳ドックはおもに脳血管疾患の早期発見が目的
・脳ドックの検査前日や当日の食事や行動に制限はないが、MRI検査にはさまざまな注意事項がある
・脳ドックは裸眼、ノーメイクでの受診が基本
・閉所が苦手な方は圧迫感が少ないオープン型MRIなどの選択肢もある
目次
脳ドックの検査内容と検査でわかること
脳ドックとは、画像などから脳の異常を早期発見することを目的とした専門ドックの名称です。脳ドックには大きくスタンダードなプラン(コース)と、基本に加えより専門的な検査を実施するプラン(コース)があり、前者ではおもに脳卒中(脳梗塞・くも膜下出血・脳出血)を始めとする脳血管疾患の兆候やリスクを調べる検査が行われます。後者はスタンダードなプランの内容に加え、動脈硬化や高血圧、糖尿病といった脳血管疾患の要因となる疾患の有無や、認知症の兆候やリスクなどを調べることが可能です。
脳ドックのスタンダードなプラン(コース)
【検査内容】
・頭部MRI/MRA検査
・頸動脈超音波(エコー)検査
【わかること】
・脳卒中(脳梗塞・くも膜下出血・脳出血)を始めとする脳血管疾患の兆候、リスク
・脳腫瘍の有無
・動脈硬化の進行具合
脳ドックの専門的なプラン(コース)
【検査内容】
・頭部MRI/MRA検査
・頸動脈超音波(エコー)検査
・血液・生化学的検査
・尿検査
・心電図検査
・ABI(血圧脈波)検査・簡易認知機能検査
・頭部CT検査
など
【わかること】
スタンダードな脳ドックに加え下記。
・動脈硬化や高血圧、糖尿病など、脳卒中のリスクファクターとなる症状や発症の有無
・不整脈(心房細動)や狭心症、心筋梗塞、心筋虚血(心臓の筋肉の血流が悪いこと)
・認知症の兆候やリスク
・脳萎縮の程度
など
脳ドックの所要時間の目安
脳ドックでは、標準的な検査として頭部MRI/MRA検査と頸動脈超音波(エコー)検査が行われます。頭部MRI/MRAとは、専用の装置を用いて磁力や電磁波をあて、脳の状態を撮影(撮像)し異変がないか調べる検査です。MRIとMRAは同じ装置を使いますが、撮影方法や部位が異なります。撮影時間は約20~30分が標準的ですが、装置によっては15分程度と短い時間で撮影できるものもあります。頸動脈超音波(エコー)検査は頸動脈に超音波をあて画像化し、おもに動脈硬化の兆候などがないか調べる検査です。所要時間は約20~30分です。
上記を踏まえ、参考までにスタンダードなプランと専門的なプランの所要時間と費用の目安をまとめました。実際の所要時間や費用は検査内容や医療施設によって異なります。
【スタンダードなプラン】
所要時間:30分~2時間
費用:1.5~2.5万円
【専門的なプラン】
所要時間:30分~4時間
費用:2.5〜5万円
脳ドックの検査の流れと結果がわかる時期
脳ドックの検査の流れ
スタンダードな脳ドックの検査は、一般的に下記のような流れで進みます。なお、検査手順や流れは医療施設や検査内容によって異なることがあります。
【検査前まで】
脳ドックの検査前日および検査当日の食事や行動に関する制限はありません。検査項目に血液検査や尿検査が含まれる場合は、何らかの制限が設けられていることがあります。詳細は脳ドックを受ける医療施設に確認してください。
【検査当日の流れ】
1)予約時間までに受付、問診票に記入
2)検診着に着替える
3)MRI/MRA検査、頸動脈超音波(エコー)検査を受ける
4)医師による結果説明(医療施設による)、結果報告書は1〜3週間後に郵送で届く
5)着替え、窓口で精算し終了
検査結果は当日に説明があるケースが多い
脳ドックでは、検査終了後に画像などを見ながら医師から説明を受け、詳しい検査結果は後日郵送されるケースが一般的です。医療施設によっては、医師による結果説明が後日行われる場合や、結果説明がなく報告書の郵送のみの場合もあります。
医師による結果説明を希望する場合は、実施している医療施設を選ぶようにしましょう。
当日は裸眼&ノーメイクで受診を。脳ドックの注意事項
脳ドックで実施される頭部や頸部のMRI/MRA検査は、強い磁力を応用して撮影(撮像)を行う検査です。そのため、磁力の影響を受けやすい金属類などの持ち込みはもちろん、コンタクトレンズやメイク、マニキュアについても制限があります。カラーコンタクトレンズやメイク用品の成分に金属が含まれていることがあり、これらをつけたまま検査を受けるとやけどなどが起こる危険があるためです*1,*2 。
取り外しが可能なものは、MRI/MRA検査の前に外しましょう。ペースメーカーなど取り外しのできないものがある場合、MRI/MRA検査が受けられないことがあります。MRI/MRA検査において注意が必要なもののリストを下記にまとめました*1,*2。とくに取り外せないもの(ペースメーカー、タトゥー、アートメイクなど)がある方は、事前に必ず医療施設に伝え、指示をあおぎましょう。
【取り外しが可能なもの】
| アイテム例 | |
|---|---|
| 頭部で使用するもの | ・かつら、ウィッグ ・ヘアエクステンション ・増毛スプレー ・増毛剤 ・スプレー式白髪染め ・ヘアバレッタ(髪留め)、ヘアピン |
| 目の周辺で使用するもの | ・眼鏡 ・カラーコンタクトレンズ ・アイシャドウ ・つけまつげ ・マスカラ |
| お肌に関するもの | ・UVケア用品(クリーム、パウダー、スプレーを含む) ・金属イオン類を含む化粧品 ・ファンデーション(下地、パウダー、保湿クリームを含む) ・温熱・温感クリーム |
| 手や指に関するもの | ・指輪 ・マニキュア ・ネイルアート、つけ爪 ・ジェルネイル、アクリルネイル |
| 身体に着けるもの | ・アクセサリー ・ピアス、ボディピアス ・マスク(金属が入っているもの) ・貼るタイプの磁気治療器 ・各種カイロ ・各種貼付剤 ・テーピング |
| 衣類 | ・金属や金属糸が使われているもの ・ファスナー、ホックなど金属がついているもの ・ブラジャー ・保温用下着、矯正下着 |
| その他 | ・携帯電話、スマートフォン、タブレット端末 ・財布、紙幣クリップ ・小銭、コイン、メダル ・磁気カード(IDカード、キャッシュカード、クレジットカードなど) ・時計 ・鍵 ・金属小物(ライター、ポケットナイフなど) ・文房具(ペン、鉛筆、クリップ、安全ピンなど) ・杖、松葉杖(全木製はOK) ・筋力トレーニング用のウエイト(砂のう) ・素材のわからないもの |
【取り外しができないもの】
| アイテム例 | |
|---|---|
| 医療機器など | ・心臓ペースメーカーおよびリード ・各種ステント ・除細動器 ・刺激電極 ・シャント ・人工内耳 ・補聴器 ・脳動脈瘤手術用クリップ、体内にあるクリップ |
| ファッション・美容に関するもの | ・刺青、タトゥー ・アートメイク ・美容整形などで埋め込まれた金属糸など |
| 歯科治療に関するもの | ・インプラント ・差し歯 ・本格矯正装置(マルチブラケットシステム) ・歯科用磁性インプラント |
| 怪我などの治療に関するもの | ・磁力装着義眼 ・義肢 ・骨折治療用金属ボルト ・プレートロット ・人工骨、人工関節(チタン製を除く) ・ハローベスト ・事故などで眼や体内に金属片や金属粉が入っている方 |
上記リストにあるように、UVケア用品やアイシャドウにも金属が含まれていることがあるため、検査の当日はノーメイクが基本です。ノーメイクでの外出が憚られる方は、シートタイプのクレンジング剤などを持参し医療施設で落としてもよいでしょう。ただし、まつげエクステンションなどその場で除去できないものは事前にオフしておきましょう。カラーではないコンタクトレンズは磁性体成分をほとんど含んでいませんが*2、検査中の乾燥やずれなどを防ぐため、外すように指示されるケースがあります。アクセサリーや貴金属類はすべて外します。衣類は医療施設が用意した検査着を身に着けることが一般的なため、あまり気にしなくても問題ありません。
なお、脳ドックのMRI/MRA検査は頭部のみを検査します。医療施設によっては、タトゥーが入っていても検査が可能 としているところもあります。取り外しができないものがある場合、必ず事前に医療施設へ相談しましょう。
閉所が苦手な方は要チェック。圧迫感が少ないオープン型など、MRIの種類と特徴を解説
閉所や大きな音が不安な方の対処法
頭部MRI/MRA検査は、寝台に寝た姿勢で専用装置に入り脳の状態を撮影(撮像)する検査です。痛みもなく、X線を使わないため医療被爆の心配もありません。一方で、狭い空間や大きな音に苦手意識を持つ方もいます。閉所や大きな音への不安を少しでもやわらげるための対処法を紹介します。
・あらかじめ医療施設に不安事項を伝えておく
予約時または検査前の問診の際に、不安なことを伝えておきましょう。撮影枚数を少なくし検査時間を短縮する、アイマスクや耳栓で閉塞感や音量をおさえる、担当者が受診者に頻繁に話しかけ不安をやわらげるなど、なんらかの対応を行っている医療施設もあります。
・水を飲んでから検査する
緊張や不安をおぼえると喉が渇きやすくなります。検査の前に水を一杯飲み、喉を潤しておくことで、わずかながら緊張の緩和につながるとされています。
MRIの種類と特徴
MRI/MRA装置(以下、MRI装置)には大きく「トンネル型(ドーナツ型)」と「オープン型」の2つのタイプがあり、トンネル型にもいくつかの種類があります(2022年11月現在)。下記にそれぞれの特徴をまとめました。脳ドックを受ける際の参考にしてください。
なお、磁力をあらわすテスラは数値が大きいほど質の高い画像を描出できます。ただし、検査部位や目的によっては数値が小さいほうが適している場合もあり、また数値が大きいほど金属によるやけどなどへの注意が必要になります。

トンネル型(ドーナツ型)MRI(磁力の目安:1.5~3テスラ)
トンネル型MRIは、寝台に仰向けに寝た状態でドーム状の装置の内部に入っていくタイプです。後述するオープン型MRIと比べて磁力が強いことから、精密な画像を撮影(撮像)できます。一方、狭い空間で数十分間じっとしていること、頭にかぶせる機器(コイル)による圧迫感、独特の大きな機械音に不安感をおぼえる方もいます。
このような従来のトンネル型MRIの圧迫感や大きな音を緩和し、検査の時間をより快適に過ごせるよう、トンネル部分を広めに設計し映像や音楽を視聴できるシステムを搭載したトンネル型も登場しています。
また、コイルにはかぶせるタイプのほか乗せるタイプや巻くタイプがあり、検査内容や部位に応じて使い分けます。頭部の検査では剣道の面のようなコイルをかぶせることが一般的ですが、上部が開いたお椀状のコイルに頭を入れるタイプのトンネル型もあります。
映像システムが搭載されたタイプやお椀状コイルタイプは、従来のトンネル型の欠点をカバーすべく改良された新しいMRI装置ですが、導入している医療施設がまだ少ないため、受診機会が限られます。
オープン型MRI(磁力の目安:0.25~0.4テスラ)
両端が開けたコの字型の装置に頭部を差し込むようなイメージで撮影(撮像)するタイプです。頭部のみを差し込むスタイルのため、全身が装置に入るトンネル型より開放感があり、検査音が軽減されています。また、医療施設によってはタトゥーがあっても検査可能としている場合があります。
デメリットはトンネル型より磁力が小さいため、撮影画像の質が若干低下する点です。トンネル型の閉所感や大きな機械音がどうしても苦手な方は、メリットとデメリットを理解のうえでオープン型を選択肢に加えてもよいでしょう。
いずれのMRI装置も一長一短があります。これらを踏まえ、自身が希望するMRI装置が医療施設に備わっているかどうかも予約前に確認しておくとよいでしょう。
参考資料
*1.日本画像医療システム工業会「磁性体(金属等)持っていませんか?」(2022年)
*2.日本磁気共鳴専門技術者認定機構「市民の皆さまへ 安心してMRI検査を受けていただくために」