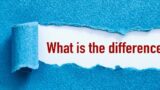人間ドックの受診後は、基本的には普段通りの生活で問題ありませんが、検査内容によっては食事や行動が制限されるなど、留意しておきたい点もあります。人間ドック当日の基本的な流れと所要時間、検査前日から検査後の注意事項を紹介します。
★こんな人に読んでほしい!
・人間ドックの当日の流れや所要時間を知りたい方
・人間ドック受診後の食事や運動、飲酒などに制限があるか知りたい方
・人間ドックを受診したあと、出社や運転をしても問題がないか知りたい方
★この記事のポイント
・人間ドックの所要時間は1~3時間程度が一般的
・胃X線(レントゲン)検査後は下剤が処方されるため、配慮のうえ予定を組もう。また、バリウムの排出を促すためにアルコールやカフェインは控えよう
・経口での胃内視鏡(胃カメラ)検査を受けた場合、喉に痛みや違和感が残ることも。また生検(組織検査)をした場合はアルコールや刺激物を控え、消化のよい食事を心がけよう
・内視鏡検査で鎮静剤を使用した場合、検査後に眠気やふらつきが残ることも。車などの運転や注意力を要する作業は控えよう
日帰り(半日・1日)人間ドックの検査項目と所要時間
人間ドックの基本的な検査項目
人間ドックは病気の早期発見や健康維持のために受ける任意の健康診断です。企業(会社)が従業員を対象に行う定期健康診断のように、実施や受診が法的に義務づけられているものではありませんが、自身の気がかりに応じて検査を選択できるため、よりパーソナルに全身の健康状態を調べることが可能になります。人間ドックの検査項目やプランなどは人間ドックを実施する医療施設によってさまざまですが、日本人間ドック・予防医療学会は下記を基本的な検査項目としています*1。
【検査項目】
- 身体測定:身長、体重、肥満度、BMI、腹囲
- 血圧測定
- 心電図、心拍数、呼吸機能
- 眼底、眼圧、視力、聴力
- X線(レントゲン):胸部、上部消化管(食道・胃・十二指腸)
- 腹部超音波(エコー):肝臓(脾臓を含む)・胆のう・膵臓・腎臓・腹部大動脈
- 血液検査
・肝臓系:総蛋白(TP)、アルブミン、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、ALP、総ビリルビン
・腎臓系:クレアチニン、eGFR、尿酸
・脂質系:総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、Non-HDLコレステロール、中性脂肪(TG/トリグリセリド)
・糖代謝系:血糖(空腹時)、HbA1c
・血球系:赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、MCV(平均赤血球容積)、MCH(平均赤血球血色素量)、MCHC(平均赤血球血色素濃度)、血小板数、血液型※
感染症系:CRP(C反応性蛋白)、HBs抗原※ - 尿検査(一般・沈渣※):蛋白、尿糖、潜血など
- 便潜血検査
※は本人の申し出または状況に応じて省略可
人間ドックを実施している医療施設の多くが、スタンダードな人間ドックとして上記の検査を実施しています。なお、医療施設によっては胃X線(レントゲン)検査を追加料金で胃内視鏡(胃カメラ)検査に変更したり、基本検査以外の検査をオプションで追加したりすることもできます。
人間ドックと健康診断の違い、受けたい検査は下記記事で解説しています。
人間ドックの半日コース・1日コースの違いとは?
人間ドックのコース・プラン名に「半日」「1日」「日帰り」などの冠がついたものがありますが、これらは所要時間などによって名称が定義されているわけではありません。
コース・プラン名は医療施設が独自に設定しているものであり、半日ドックは午前中で終わり、1日ドックは午後までかかるというわけではなく、「1日コース」と書かれていても所要時間は3時間程度の場合もあります。人間ドックを選ぶときはコース・プラン名にとらわれず、検査項目や所要時間を確認するとよいでしょう。
「半日」「1日」「日帰り」「宿泊」人間ドックの違いは下記で詳しく解説しています。
日帰り・1日人間ドックの所要時間
人間ドックの基本的な検査プランのみの所要時間は、1〜3時間程度です。
脳ドックや乳がん検査、子宮頸がん検査など、基本的な検査以外の検査を組み合わせて同日に受ける場合は、その分の時間が上乗せされます。とくに、胃内視鏡(胃カメラ)検査や大腸内視鏡(大腸カメラ)検査は体内にカメラを入れるため他の検査より時間を要します。また、内視鏡検査の際に鎮静剤を使用する場合は、検査後に30分〜1時間程度の安静時間が必要となるため、トータルの所要時間も延びます。
人間ドックの所要時間は医療施設の混雑状況などによっても前後するため、受診日は余裕を持ったスケジューリングが望ましいでしょう。
リフレッシュを兼ねてじっくり人間ドックを受けてみたい方は、ホテルや温泉宿などに泊まる「宿泊ドック」もチェックしてみてください。
人間ドックは午前と午後、どちらがよい?
人間ドックの受診は、午前中より午後のほうが予約を取りやすく、待ち時間も短い傾向にあります。
人間ドック受診が午前の場合、前日の夜21時ごろからの絶食が一般的ですが、午後受診の場合、食パン1枚程度の朝食はとってもよいとする医療施設が多いため、午前受診に比べ絶食時間が短くすむ場合もあります。
前日までに準備することと注意事項
提出書類等への記入
人間ドックに申し込むと、医療施設から人間ドックについての案内や検査容器等が送付されます。事前に注意事項などに目を通し、問診票や検査の同意書などの書類に記入しておきましょう。既往歴、家族歴(家族の既往歴)、内服薬など健康上の気がかりがあれば、問診票で申告できます。最近はWeb問診システムを導入している医療施設も増えつつあります。回答期限を守って入力をすませましょう。
便潜血検査(検便)の検体の採取
便潜血検査は大腸のがん、潰瘍、ポリープなどに由来する出血が便に含まれていないかを調べる検査です。出血が微量だと毎回の便には混入しないこともあるため、厚生労働省は大腸がん検診として2回分の便を調べる「2日法」を推奨しており*2、人間ドックでも基本的に2回分の便を採取します。便の採取は人間ドック当日を含む3日以内が望ましいとされていますが*3、重い便秘などで2回分の採取が難しい方は医療施設に相談しましょう。当日の朝までにどうしても2回分の採取ができなかった場合は、検便のみ後日の提出を指示されることもあります。
便潜血検査については、下記記事もご参照ください。
前日の過ごし方の注意事項まとめ
人間ドック前日のおもな注意点は下記です。
前日の食事
正確な検査結果を得るため、人間ドックや健康診断では一般的に空腹時(10時間以上の絶食後)に採血を行います。また、胃X線(レントゲン)や胃内視鏡(胃カメラ)検査の前には胃を空にしておく必要があります。午前中に人間ドックの予約をしている場合は、前日の21時ごろまでに夕食をすませましょう。
アルコールも検査に影響します。前日から禁酒としている医療施設が多いですが、アルコールの代謝のスピードには個人差があるため数日前から飲酒量を調整したほうがよい場合もあります。
水やお茶は就寝まで飲んでかまいません。
前日の運動
前日に激しい運動を行うと、血液検査で肝機能や腎機能の数値に影響が出ることがあります。日頃運動習慣がない方は、体重などが気がかりでも前日に追い込むような運動はせず、普段通りの生活を心がけましょう。
注意事項を守れなかった場合は、検査を受けても正確な結果が得られないことがあります。医療施設から送付される注意事項をしっかり読み、もしうっかり守れなかった場合は医療施設に申し出ましょう。
人間ドック前日の過ごし方についての詳細は、下記記事をご参照ください。
直前でキャンセルしたい場合の料金は?
人間ドックは自由診療のため、直前でキャンセルした場合に料金がかかるかどうかは医療施設によって異なります。当日キャンセルでも料金はかからない医療施設もあれば、旅行のように予約の数日~数週間前からキャンセル料が発生し、当日のキャンセル料は料金全額を請求するとしている医療施設もあるため、予約時などに確認しておきましょう。万一、前日や当日になって急に体調が悪くなってしまったら、自己判断でキャンセルせず医療施設に問い合わせましょう。風邪のような症状や発熱のある場合は、別日に延期となることもあります。
日帰り(1日)人間ドック当日の流れ
当日検査前の注意事項
人間ドック当日の朝~検査前は次の点に注意してください。
当日の食事
午前中の予約であれば、当日は朝食を抜くことが基本です。飴やガムも血糖値に影響するので口にしないようにしましょう。
予約が午後の場合、朝7時頃までに食パン1〜2枚程度の軽い朝食を食べてよいとしている医療施設もあります。食事に関する指示を確認するとよいでしょう。ヨーグルト、チーズ、バターなどの乳製品は胃の粘膜をおおって検査に影響することがあるので、避けるようにしましょう。
飲み物については多くの医療施設が、脱水を防ぐために検査の2時間くらい前までにコップ1杯(200ml)程度の水または白湯を飲んでよいとしています。糖分やカフェインの入った飲み物は避けましょう。
当日の喫煙
たばこは血管の収縮や胃酸の分泌を促し、血糖値にも影響を及ぼします*4,*5。血圧測定、血液検査、心電図、胃のX線(レントゲン)や内視鏡(胃カメラ)などの検査を正確に実施できないおそれがあるため、検査当日は禁煙としている医療施設が多いです。IQOS(アイコス)やglo(グロー)などの加熱式たばこにもニコチンが含まれているので、禁煙を心がけましょう*6。
当日の服薬
糖尿病の治療で血糖値を下げる薬を使用している方は、絶食中は薬を中止することがあります*7。
高血圧、心臓病、うつ病、パーキンソン病、てんかんの薬は、当日受付の2時間前までに、コップ半分程度の量の水で服用してください*7。
血液を固まりにくくする薬(抗凝固薬)を飲んでいる方は、胃内視鏡(胃カメラ)検査で生検(組織検査)をした際の出血に注意が必要です。事前に主治医に相談し、検査の前に受診先にも申告するようにしましょう。
そのほか、喘息の薬など飲まないと症状が悪化する薬については、検査の前に飲んでもよいとしている医療施設もあります。服薬中の薬がある方は、事前に主治医ならびに人間ドックを受ける医療施設に確認しましょう。
当日の運動
激しい運動は血液検査や尿検査に影響する可能性があります。毎日のルーティンとして筋トレやランニングなどをしている方は、検査当日の朝に運動してもよいか事前に医療施設まで問い合わせておきましょう。
その他
胃内視鏡(胃カメラ)検査では、苦痛や過度な緊張を和らげるために鎮静剤を使用することがあります。健康管理のために顔色を観察したり、指にパルスオキシメーター(血中の酸素濃度を測る装置)をはめたりすることがあるため、メイクを控えめにし、マニキュアはしないよう指示されることがあります。
注意事項は当日受ける検査によって、また医療施設によっても異なります。詳しくは医療施設から配布される資料等を確認しましょう。
人間ドックの服装やメイクについては、下記で詳しく解説しています。
人間ドックの持ち物は下記記事をご覧ください。
スタンダードな人間ドックの流れ
受付から終了までのおおよその流れを紹介します。
【医療施設に行く前】
朝起きてすぐの尿を自宅で採取します。採尿は医療施設で行うこともあります。
人間ドックでは、指定された検査着に着替えるのが一般的ですが、施設によっては私服のまま検査を受けることもあります。上下セパレートで脱ぎ着のしやすい服で臨むと検査がスムーズです。
【受付】
持参した問診票や検体を受付で提出します。
【着替え】
更衣室で用意されている検査着に着替えます。
【問診・診察】
医師による問診を受けます。既往歴、家族歴、飲んでいる薬などのほか、気がかりがあれば話しておきましょう。
【検査】
検査の順序は医療施設により異なります。一例として参考にしてください。
- 計測:身長、体重、BMI、体脂肪率、腹囲、視力、聴力、血圧などを計測します。
- 心電図:胸に電極パッチをつけて心臓の動きを測り、不整脈や心肥大、狭心症などの心臓疾患を疑う異変がないかを調べます。
- 肺機能:スパイロメーターという装置で呼吸について調べます。気管支炎や肺気腫などの肺疾患の発見につながる検査です。
- 胸部X線(レントゲン)※:肺炎、肺結核、肺がんなどの肺疾患ならびに、心臓疾患について調べる検査です。
- 胃X線(レントゲン)※:バリウムを飲んで食道、胃、十二指腸を撮影し、がんや潰瘍などの兆候を調べる検査です。胃X線検査のかわりに、胃内視鏡(胃カメラ)検査を行うこともあります。
- 腹部超音波(エコー):腹部に検査用のゼリーを塗り、超音波装置を当てて肝臓や腎臓を観察します。
※妊娠中の方、妊娠の可能性がある方はX線(レントゲン)検査を受けられないため、申告しましょう。
【結果説明】
結果の通知方法は医療施設により異なりますが、日本人間ドック・予防医療学会が認定した「機能評価認定施設*8」では、当日に医師より簡単な結果説明があり、詳しい結果は後日郵送されるのが一般的です。
医療施設によっては、必要に応じた保健指導(生活のアドバイス)や受診後のフォローアップも受けることができます。
人間ドックの待ち時間にスマホを触ってもよい?
医療施設によって異なります。スマホやタブレットの閲覧はよいが、通話や検査室へのスマホの持ち込みはNG、パソコンは持ち込めないなど、なんらかのルールを設定している医療施設が多いです。
待ち時間にスマホを使いたい、タブレットなどで仕事をしたい場合は、事前に確認しておきましょう。
人間ドック受診後の注意事項
検査後人間ドック受診後は、どんな食事がよい? アルコールはOK?
人間ドックを受診した後は、基本的には普段の食事に戻ってかまいません。ただし、胃の検査を受けた方は次の点に注意が必要です。
胃X線(レントゲン)検査でバリウムを服用した方
バリウムの排出を促すために、水分を多めに飲みましょう。消化のよい水溶性食物繊維(切り干し大根、干し椎茸、納豆など*9)を摂るよう意識するとよいでしょう。
アルコールやカフェイン入りの飲み物(コーヒー、紅茶など)には利尿作用があり、便を出すのに必要な水分まで尿として排出してしまうことがあります。翌日まで控えるようにしましょう。
胃内視鏡(胃カメラ)検査を受けた方
口から内視鏡を入れる経口検査と、鼻から入れる経鼻検査とで、食事が再開できる見込み時間が少し異なります。
- 経口検査:喉の局所麻酔が切れるまで、1〜2時間は飲食ができません。水を少量飲んでみて、むせなければ飲食が可能です。
- 経鼻検査:鼻の局所麻酔のみで検査をした場合、飲食は30分~1時間後から可能です。
検査中に生検(組織検査)のために組織を採取した場合は、2~3日程度アルコールを控え、刺激が少なく、消化のよい食事を心がけましょう。
運動・入浴について
スタンダードな人間ドックの場合、検査後の運動や入浴について大きな制限はありません。参考までに、血液検査の採血量は通常大さじ1杯(15ml)ほどで、献血時の採血量400ml(体重50kg以上)*10と比較してもわずかです。人の活動に差し障る量ではないと考えて問題ありません。
なお、胃内視鏡(胃カメラ)検査を受けた場合、検査後の運動や入浴については、制限を設けていない施設もあれば、激しい運動は避け、入浴はシャワーですませるよう指示しているケースもあるなど医療施設によってまちまちです。胃内視鏡(胃カメラ)検査後に運動をしたい場合は、事前に医療施設に問い合わせておきましょう。
受診後の出社や運転は控えたほうがいい?
スタンダードな人間ドックの所要時間は1~3時間程度です。午前中に受診し、午後から出社やお出かけなどを予定する場合、次の点に留意しましょう。
胃X線(レントゲン)検査を受けた方
バリウムの排出を促すために下剤が処方されます。トイレが頻回になる可能性を考慮のうえ、予定を調整しましょう。
胃内視鏡(胃カメラ)検査を受けた方
喉や鼻の局所麻酔のほかに鎮静剤を使用して検査を受けた場合、検査後も眠気やふらつきが残るため、1〜2時間ほど医療施設で休むことがあります。また、鎮静剤の影響を考慮し、検査後の車の運転(自転車やバイク含む)は不可とする医療施設が一般的です。受診時は公共交通機関やタクシーを利用するか、家族や知人に送迎してもらう手はずを整えましょう。さらに、医療施設によっては高所での作業、集中力を要する作業などを控えるよう呼びかけていることもあります。
経口(口から内視鏡を入れる)で検査を受けた場合は、喉の腫れや声のかすれなどの違和感が残ることがあります。プレゼンなど、大きな声で話す必要がある予定などは控えたほうが無難でしょう。
人間ドックは検査前だけでなく、検査後も食事や行動が制限されることがあります。注意事項を確認し、無理のない予定を組むようにしましょう。
参考資料
*1.日本人間ドック・予防医療学会 基本検査項目/判定区分
*2.国立がん研究センター がん情報サービス 大腸がん(結腸がん・直腸がん)予防・検診
*3.日本予防医学協会 健康診断よくある質問[健診前_09]便潜血検査の検体は何日前から採取可能ですか?
*4.喫煙科学研究財団 喫煙と消化器系
*5.厚生労働省 e-ヘルスネット 喫煙と糖尿病
*6.東京都医師会「タバコQ&A(改訂第2版)」
*7.日本総合健診医学会 総合健診を受診される方へ 12.健診の上手な受け方(Q&A)
*8.日本人間ドック健診協会 e人間ドック 健診と人間ドックの違い
*9.長寿科学振興財団 健康長寿ネット 食物繊維の働きと1日の摂取量
*10.厚生労働省 採血基準