子宮頸がんは女性特有のがんで、年間の死亡者数は約2900人と言います*1。また、子宮頸がんは比較的若年層にも多いがんで、20代での罹患も少なくありません。症状に乏しいため、発見は定期的な子宮頸がん検診が有効とされています。
この記事では、子宮頸がんの概要のほか、がん検診の内容、推奨される受診頻度とその理由について紹介します。
★こんな人に読んでほしい!
・20代後半以上の女性
・子宮頸がん検診を何年おきに受けたらよいか知りたい女性
・おすすめの施設の選び方を知りたい女性
★この記事のポイント
・子宮頸がんの好発年齢は20代から40代の若年層
・子宮頸がんのおもな原因はヒトパピローマウイルスへの感染
・子宮頸がんの推奨受診頻度は2年に1度
・妊娠・出産やその他条件によってはそれ以上の頻度での受診が奨められる場合も
・子宮頸がん検診を受ける医療施設の選び方
目次
子宮頸がんは20代から40代の若い世代に増加している
子宮頸がんは、女性にとって無視することのできないがんのひとつです。日本において新たに子宮頸がんと診断される人の数は年間約1万1000人(2017年)、子宮頸がんで死亡する女性の数は年間約2900人(2019年)です*1。
一般的にがんのリスクが高まるのは40代からと言われていますが、子宮頸がんの場合、20代・30代といった若い世代においても発症リスクが高く、40代でピークを迎えます。とくに20代・30代での罹患者数は1990年から2015年前後にかけて約2倍に増える*2など、増加傾向にあります。そのため、子宮頸がんに関しては、20歳を過ぎたら定期的ながん検診の受診が強く勧められます。
子宮頸がんのおもな原因は性交渉によるヒトパピローマウイルスへの感染
ヒトパピローマウイルスとは
子宮頸がんの95%以上はヒトパピローマウイルス(HPV)への感染が原因であると言われています*3。HPVは、人から人へと伝染するウイルスのひとつです。おもに性交渉によって感染するウイルスで、男性・女性ともに感染の可能性があります。温泉やプールなどで伝染することはありません。
HPVはごくありふれたウイルスで、性交経験のある女性の50〜80%が生涯のうちに一度は感染すると言われています*3。感染した人が全員子宮頸がんになるわけではなく、ほとんどの場合感染は一過性で、免疫機能により2年以内に消滅すると言われています。しかし、HPVのうち、特定のハイリスクな型(16型と18型がもっとも多い)に関した場合、持続感染となることがあります。このように感染が長期化するケースなどさまざまな理由において、一部子宮頸がんに移行することがあります。
初期症状がほとんどないため検診を受けることが重要
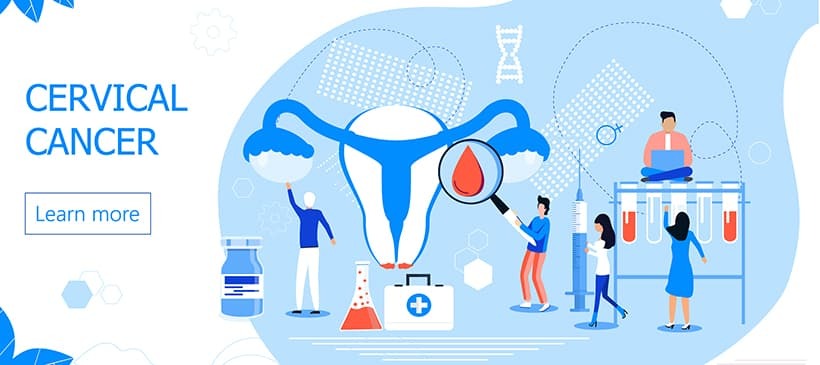
注意したいのは、HPVは感染しても症状がほとんど現れないウイルスであるという点です。そのため、感染していても自分では気づいていないことがほとんどです。また、子宮頸がんに移行すると症状が現れますが、性交時の出血やおりものの増加など目立たないものが多く、見逃されがちです。初期の子宮頸がんに自分で気づくことは困難です。
一方で、子宮頸がんはがんのなかでもとくに早期発見の重要性が高いがんでもあります。がんが進行してしまうと治療が困難になるだけでなく、子宮や卵巣といった妊娠・出産に関わる重要な臓器を摘出しなくてはならなくなる可能性があります。しかし、早期の子宮頸がん、あるいは前がん病変と呼ばれる段階で発見することができれば、子宮頸部円錐切除術や子宮頸部レーザー蒸散術といった治療法を取ることができます。これらの治療範囲は子宮頸部に限局した比較的せまい範囲であるため、その後の妊娠・出産に与える影響が比較的少ない治療法です。
上記の理由から、子宮頸がんは早期発見・早期治療の重要性がとても高いと言えます。HPVは母子感染も指摘されているため*4、20歳を過ぎたら性交渉の有無に関わらず定期的に子宮頸がん検診を受診しましょう。
子宮頸がん検診はどのくらいの頻度で受診したほうがよい?
国が推奨する子宮頸がん検診は「子宮頸部細胞診を2年に1回」
がんは発症する部位によって進行の速度や進み方が異なるため、どのがん検診を受けるかによって、推奨される受診頻度も異なります。子宮頸がん検診は2年に1回の受診が推奨されています*5。日本国内で子宮頸がんの死亡率減少効果が示されている検査は、子宮頸部細胞診とHPV検査があります。そのうち、国はがん検診として子宮頸部細胞診を推奨しています。

子宮頸部細胞診は子宮頸部の細胞を採取し、顕微鏡で調べる検査です。HPVに持続感染すると、子宮頸部にがんの前段階である細胞ができます。これを「異形成」と言います。異形性は軽度・中度・高度がありますが、高度異形成となると「前がん病変」と呼ばれます。子宮頸部細胞診ではこの前がん病変、もしくは子宮頸がんの有無を調べます。一方HPV検査では同様に子宮頸部の細胞を採取し、HPVウイルスの影響を受けている細胞の有無や数を調べます。
子宮頸がんは、がんの中で唯一予防ワクチンがあります。子宮頸がんワクチンは現在、高い予防効果が認められています。しかし、その効果も100%ではありません*6。そのため、子宮頸がんのワクチンを打っていたとしても、定期的にがん検診を受ける必要があります。
子宮頸部細胞診で異常が発見されたら必ず医療機関の受診を
子宮頸がん検診で推奨されている子宮頸部細胞診は、子宮頸がんによる死亡率の減少効果が認められています。がん検診を積極的に行った地域では、そうでない地域に比べて子宮頸がんでの死亡率減少幅が大きかったという研究成果もあります*7。
一方で、すべての医療検査に言えることですが、子宮頸部細胞診も検査精度は100%ではありません。子宮頸部細胞診で高度異形成・上皮内がん以上の病変を見つけられる精度は約70%と言われています*7。
子宮頸部細胞診で異常が発見された場合には、その結果に応じて経過観察、もしくは精密検査となります。精密検査では、HPV検査やコルポスコープ検査を行います。HPV検査は、子宮頸部の細胞を採取し、HPVに感染していないかを調べる検査です。コルポスコープ検査は、コルポスコープと呼ばれる拡大鏡を挿入し、子宮頸部の状態を確認する検査です。どの検査を追加で行うか、あるいは経過観察でよいのかは検診の結果に基づいて医師が判断します。

子宮頸がん検診の検査手法
子宮頸がんの早期発見を目指すには、定期的な検診受診が大切です。推奨される受診頻度は受ける検査の内容や年齢によって異なります。国立がん研究センターは、それぞれの検査について推奨頻度を次のように示しています*8。
| 検査手法 | 受診頻度 | 対象年齢 | ガイドラインでの推奨グレード |
| 子宮頸部細胞診のみ | 2年に1回 | 20〜69歳 | A(利益がある) |
| HPV検査のみ | 5年に1回 | 30〜60歳 | A(利益がある) |
| 子宮頸部細胞診とHPV検査を併用 | 5年に1回 | 30〜60歳 | C(利益があるが不利益が大きい) |
子宮頸部細胞診のみの場合
子宮頸部細胞診のみの子宮頸がん検診は、もっとも広い年齢層に適しており、国として推奨されている検査手法でもあります。子宮頸部の細胞を採取し、前がん病変や子宮頸がんの有無を調べるため、検査としての精度も比較的高いです。ただし、子宮頸部細胞診はウイルスを保持しているかどうかの検査ではなく、発症の有無や兆候を見る検査です。一度検査したからその後ずっと大丈夫、ということはありません。前がん病変や早期がんの状態で発見するためには、少なくとも2年に1回程度の頻度で定期的に受診することが望ましいです。
HPV検査のみの場合
日本では、子宮頸がん検診としては子宮頸部細胞診が推奨されています。一方で、米国では細胞診・HPV検査併用法が、ヨーロッパではHPV検査単独法が推奨されています。日本においても、HPV検査を適切に検診に活用できるよう、検査方法などの精査・研究が進められています。現状では、罹患者が増加している20歳代に適しているとはされていません。
HPV検査は、子宮頸部の細胞を採取し、HPVへの感染の有無を調べます。一般的に、HPVに感染してから前がん病変や子宮頸がんの発症までは数年あると言われています。そのため、HPV検査は細胞診に比べて推奨受診頻度は低めです。一方で、HPV検査では細胞診に比べて偽陽性(本当は病気でないのに、病気であるという結果が出ること)の確率が高くなります*8。検査で陽性と言われた場合にも、適切に医療機関を受診し、医師の指示に従って精密検査や適切な経過観察を行うことが求められます。
子宮頸部細胞診とHPV検査を併用する場合
子宮頸部細胞診とHPV検査の両方を受けるという選択肢もあります。検査を併用することで、より高い精度で病気の可能性を探ることができます。一方で、子宮頸部細胞診・HPV検査併用法では、それぞれの単独法に比べ、偽陽性が生じる可能性がもっとも高くなります*8。そのため、陽性と診断されたあとの診察や精密検査が大変重要となります。
また、子宮頸部細胞診においては、検体となる細胞をどのように採取するかも大変重要です。検査精度の向上のため、検体の採取に当たっては液状検体法、医師採取が原則となっています。液状検体法とは採取した細胞を特殊な液体の中で回収・保存する方法です。これにより、再検査や追加検査が容易となり、一度の細胞採取でより精密な検査が可能となっています。
1年に1回の子宮頸がん検診が推奨される方
前述の通り、子宮頸がん検診は2年に1回の受診が推奨されています。これ以上受けても、子宮頸がんの予防効果は変わらないとされています*9。しかし、例外もあります。たとえば、妊娠中に子宮頸がんが発見されると、治療が困難になる場合があります。とくに、進行してから発見されることで、効果を期待できる治療法が限定されてしまう可能性があり、治療法によってはその後の妊娠の継続や出産に影響が生じることもあります。そのため、妊娠・出産を希望する場合には、国の推奨よりもさらに高頻度で、1年に1回程度受診することがおすすめです。
その他、子宮頸がんの発症リスクが高まる要因に、喫煙習慣が指摘されています*10。また、「2-1. ヒトパピローマウイルスとは」で述べたとおり、HPVに感染しても多くは免疫機能により排除されますが、免疫力がもともと低いあるいは生活習慣により低くなっている時期は、HPVの排除能力が低いと考えられます。これらに当てはまる人は、ほかの人に比べてよりていねいな観察が必要となります。妊娠を希望する人と同様に、1年に1回程度の受診がおすすめです。
子宮頸がん検診で医療施設を選ぶ5つのポイント
効果的で自分にあったがん検診を受けるためには、検診を受ける医療施設選びも大変重要です。場合によっては、がん検診だけでなくその後の精密検査や治療への移行など、長い付き合いになる可能性もあります。「どこでも同じ」と安易に決めるのではなく、自分に合った医療施設で検診を受けることが、その後のスムーズな治療や、無理のない定期受診につながります。
受けたい検査項目や検査内容があることを確認
医療施設を選ぶ際には、自分が受けたい検査項目や内容を受けることができるかをしっかりと確かめましょう。検査可能な項目や内容は、医療施設によって異なります。所有している機器の違いなどもあるため、事前に具体的に確認しておくことが大切です。
細胞診・HPV検査への対応だけでなくコルポスコープも所有している施設であれば、万一精密検査が必要となった際にも同じ施設で検査を受けることができます。また、なかには細胞診において医師採取法を選択した場合に追加料金が生じる施設もありますので、合わせて確認が必要です。
産婦人科専門医、婦人科腫瘍専門医が在籍している
在籍している医師の専門性や経歴、実施可能な治療内容も確認しておくことをおすすめします。医師の専門性や施設の設備により、実施可能な治療法は異なります。万が一異常が見つかった場合でも、子宮頸がんの治療に精通した専門医が在籍していれば、精密検査や治療にスムーズに移行することができます。これまでと同じ医師に継続して治療してもらえるという点は、経過がわかっているというメリットと安心感があります。
また、その医療施設で受けることのできる治療法も選択の際の重要な指標となります。子宮頸がんの場合、前がん病変の間に発見することができれば、日帰り手術での治療が可能なケースがあります。子宮頸部レーザー蒸散法と呼ばれる治療法ですが、行える医療施設が限られているというデメリットもあります。検診を受ける際から可能な治療法を調べておくことで、万一異常が見つかった際にも安心して治療を継続することができます。
女性のプライバシーに配慮した工夫をしている
子宮頸がんの検査は、女性にとってプライベート性の高い内容です。人によっては抵抗感を感じる内容も少なくありません。気になる方は、検診にあたっては女性のプライバシーに配慮した取り組みを行なっている医療施設を選ぶとよいでしょう。
具体的には、女性医師が検診を担当している、検査時はカーテン仕切りがなされ、顔を合わせないようになっている、女性専用エリアがある、などです。検診内容や前後の対応において抵抗感がある状態となってしまうと、定期的な受診が負担になってきます。できる限り抵抗感を少なく受診を続けていけるよう、自分が安心できる雰囲気の施設を選ぶことが大切です。
通いやすい場所にある
医療施設の立地も大切な要素のひとつです。定期的な受診のためには、自宅や勤務先から近いなど、自分が通いやすい場所にある施設を選ぶことが推奨されます。とくに、検査の結果経過観察が必要となった場合、3ヶ月〜半年に1回程度の頻度で受診を続けることになります。遠方の医療施設を選んでしまうと、経過観察のための通院が負担となり、治療中断につながってしまう危険性があります。子宮頸がんを早期発見することができても、適切な観察を続けず中断してしまう事態になっては意味がありません。医療機関を選ぶ際には、無理せず通える立地の施設を選ぶようにしましょう。
日帰り治療を受けられる
子宮頸がんの前がん病変に対する治療のひとつに、子宮頸部レーザー蒸散術があります。レーザーを用いて病変部を焼く治療法で、子宮や周辺組織を温存することができます。そのため、従来法である子宮頸部円錐切除術に比べて、将来の妊娠や出産への影響がない方法として注目されています。子宮頸部円錐切除術では数日間の入院が必要となりますが、レーザー蒸散術であれば身体への負担が少ないため、日帰りあるいは1泊2日で治療が可能です。
子宮頸部レーザー蒸散術は手術にともなう出血が少なく、麻酔ではなく座薬(鎮痛薬)で手術を受けられることもメリットと言えます。しかし、新しい治療であり、行うことができる医療施設が限られているというデメリットもあります。検診を受ける医療施設を選ぶ際には、子宮頸部レーザー蒸散術の可否も検討材料とするとよいでしょう。
参考資料
*1. 国立がん研究センター がん情報サービス「がん登録・統計」最新がん統計
*2. 国立がん研究センター がん情報サービス「がん登録・統計」グラフデータベース
*3. 日本産科婦人科学会 子宮頸がん
*4. 日本小児科学会「学校、幼稚園、保育所において予防すべき感染症の解説」2020年5月改訂版
*5. 国立がん研究センター がん情報サービス 子宮頸がん
*6. 厚生労働省 HPVワクチンQ&A「Q15.HPVワクチンはどれ位効くのですか?」
*7. 国立がん研究センター がん情報サービス 子宮頸がん検診
*8. 国立がん研究センター 社会と健康研究センター「有効性評価に基づく子宮頸がん検診ガイドライン更新版」2020年3月
*9. 日本医師会「知っておきたいがん検診」子宮頸がんQ&A「Q2. なぜ子宮頸がん検診は2年に1回の間隔で良いの?」
*10. 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防グループ 喫煙と子宮頸がんリスク













