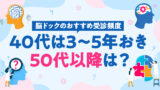脳ドックは、脳に異常がないかを調べる専門ドックのひとつです。脳卒中や認知症のリスクを調べられる一方で、「受けないほうがよい」などの反対意見もみられます。この記事では、反対意見の理由や、脳ドックを受けたほうがよい人の特徴について解説します。
★こんな人に読んでほしい!
・40歳以上の方
・脳ドックに興味がある方
・喫煙習慣や生活習慣病を有する方
★この記事のポイント
・脳ドックは、脳卒中や認知症の兆候やリスクを調べて、予防や治療につなげるきっかけにできる
・自身の年齢や、生活習慣、家族歴などにあわせて、脳ドックの受診を検討することが大切
・脳ドックはMRI/MRA検査で強い磁場を用いるため、体内に金属がある方など注意が必要
・脳ドックを受けた方の体験談では、「検査はスムーズだった」「異常がなく安心できた」などのポジティブな意見が多くみられた
目次
脳ドックとは? 「受けないほうがよい」は本当?
脳ドックは、脳の病気の兆候や発症リスクを早期発見できる
脳ドックとは、脳の状態を詳しく調べられる専門ドックです。一般的な人間ドックには含まれていない頭部MRI/MRA検査や頸動脈エコー検査などを組み合わせて使用することで、脳に関係する疾患の有無や兆候を調べることができます*1。
脳ドックで発見できる疾患には、症状を起こしていない脳梗塞(無症候性脳梗塞)や微小出血、くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤、脳腫瘍、頭に血液を送る頸動脈の狭窄などがあります*1。また、脳ドックのより詳細な検査を含むプラン・コースでは、アルツハイマー型認知症に特徴的な脳の萎縮パターンを評価するVSRAD®が含まれることもあります。
加齢にともないとくに多く認められる脳の病気が、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血の総称である脳血管疾患(脳卒中)や認知症です。脳卒中は発症すると、突然死や重大な後遺症につながるリスクがあります。厚生労働省の統計において、日本人の全死因の上位に脳卒中が位置しており、介護が必要になる原因では第2位となっています*2,*3。
また、介護が必要になる原因の第1位が認知症です*3。認知症は今後の治療や生活設計のためにも早期の診断・治療が重要です。認知症の前段階である「軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)」の状態で早期に発見し、生活習慣の見直しや治療介入を行うことで、認知機能の低下を遅らせることができる可能性があります*4。脳ドックの受診は、脳卒中や認知症の兆候・リスクを把握し、適切な予防や治療につなげるきっかけとなり得ます。
脳ドックについては下記で詳しく解説しています。
アルツハイマー型認知症のリスクを調べる「VSRAD®︎」について知りたい方は、下記記事をご覧ください。
「脳ドックは受けないほうがよい」という意見がある理由
「脳ドックは受けないほうがよい」という意見がある理由には、以下のようなものが挙げられます。
1)受診費用が比較的高額
脳ドックの費用目安は、基本的なプラン・コースで1.5~2.5万円程度、より詳細な検査を含むプラン・コースは2.5~5万円程度です。保険適用外のため、負担に感じる方がいるかもしれません。なお、加入している健康保険組合や自治体によっては助成・補助制度を設けていることがあるため、事前に確認するとよいでしょう。詳細は以下の記事をご覧ください。
2)診断精度が100%ではない
どんな検査でも言えることですが、脳ドックの検査精度は100%ではありません。例えば、下記のようなことが起こる可能性もあります。
- 見つけにくい部位の脳動脈瘤が見落とされる(偽陰性)
- 脳卒中の兆候がなくても脳卒中の疑いがあると診断される(偽陽性)
- 発見されなくても生命に影響のない所見が病気として診断される(過剰診断)
など
脳ドックはあくまで予防や早期発見のためのひとつの手段であり、その後の精密な検査による正しい診断が重要です。
3)MRI検査にともなう圧迫感
MRI検査はトンネル型の装置内で大きな音がする検査のため、閉所恐怖症の方には強い圧迫感や恐怖感が生じることがあります。しかし、最近では開口部が広く、音もトンネル型より静かな「オープン型MRI」を導入する医療施設が増えています。閉所や大きな音が苦手な方は検討するとよいでしょう。
4)待ち時間の長さ
脳ドックの所要時間は、脳血管疾患の検査が中心の基本的なプラン・コースで約2時間程度です。しかし最近では、待ち時間短縮に取り組む医療施設も増えており、基本的なプラン・コースが30分程度で完了することもあるなど、忙しい方でも受診しやすくなっています。
5)病気が発見された場合の精神的な負担
脳ドックを受けて病気が発見された場合、想像以上にショックを受ける可能性があります。例えば、脳ドックで見つかることがある未破裂脳動脈瘤は、破裂するとくも膜下出血となりますが、破裂率は決して高くなく、治療に進むかどうかという難しい選択を迫られることがあります。
脳ドックを受けるとこうした事態が起こることを理解しておき、またもし異変が見つかった場合に自身がどうしたいかまで考えておくことが大切です。
脳ドックを受ける前に知っておきたいデメリットは、以下の記事で詳しく紹介しています。
脳ドックを受けたほうがよい人の特徴
以下のような特徴を持つ方は、脳ドックの受診の検討をおすすめします*1。
- 中高年者
- 喫煙習慣がある方
- 高血圧、糖尿病または脂質異常症などの生活習慣病の方
- 肥満気味の方
- 脳卒中や認知症の家族歴がある方
上記の方は、将来的に脳卒中や認知症などの脳疾患になるリスクが高いことがわかっています。次項でそれぞれ詳しく解説します。
脳卒中と呼ばれる3つの疾患、脳梗塞・脳出血・くも膜下についてはそれぞれ、下記記事で詳しく解説しています。
中高年者
脳梗塞や脳出血を発症するリスクのひとつが「動脈硬化」です。動脈硬化は血管が厚く硬くなった状態のことで、加齢や喫煙、脂質異常症、高血圧、糖尿病などが危険因子です*5。日本脳卒中データバンク(2024年)によれば、脳卒中発症率は30代までの若い方ではわずかですが、40代から徐々に増加し始め、70~80代で最も多い傾向にあります*6。
認知症も加齢にともない増加する病気です。2022〜2023年に実施された大規模調査では、65〜69歳の認知症有病率は1.1%であるものの、80〜84歳は16.6%、90歳以上になると50.3%というデータが報告されています*7。
脳卒中など脳の病気の予防や早期発見の観点から、脳ドックは40代以降の定期的な受診が望ましいと言えます。ただし、20代や30代でも受診したほうがよいケースもあります。詳細は以下の記事をご覧ください。
40代、50代など年代別の脳ドック受診間隔の目安は下記記事で解説しています。
喫煙習慣がある方
喫煙は、呼吸器系の病気をはじめ、さまざまな病気のリスク因子として知られていますが、脳卒中においてもリスクとなります*8。たばこに含まれるニコチンなどの有害物質は血管を収縮させ、動脈硬化や血栓の形成を引き起こすためです*9。2009年の国内の研究データによると、喫煙者は非喫煙者と比較して脳卒中のリスクが男性で1.24倍、女性で1.70倍高いことが明らかになっています*9。
また、喫煙は認知症のリスクを高めることも示唆されています。そのメカニズムはまだ明らかになっていませんが、喫煙による酸化ストレスの増加が脳に影響することなどが考えられています*8。
喫煙している方は、自覚症状はなくても、脳ドックで脳の状態をチェックしてみるとよいでしょう。
高血圧・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病がある方
高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病は、動脈硬化のリスク因子であり、脳梗塞や脳出血につながる恐れがあります*5。とくに高血圧は、脳卒中の最大の原因と考えられており、収縮期血圧が10mmHg上昇するごとに、脳卒中および死亡のリスクは男性で約20%、女性で約15%増加するとされています*10。
生活習慣病は、健康的な食生活や定期的な運動による対策が大切です。血圧については下記で詳しく解説しています。
肥満気味の方
肥満(BMI25以上)は高血圧、糖尿病、脂質異常症などの発症リスクを高めることに加え、脳梗塞の発症リスクになることもわかっています*11。日本人を対象とした大規模研究によれば、BMI30以上の方は、標準のBMI(23~25未満)の方に比べて、脳梗塞の発症リスクは1.69~1.99倍高いことが報告されています*12。
太り気味、あるいは肥満が気になっている方は 、食事や運動習慣の見直しに加え、定期的に脳の状態もチェックしていくことが勧められます。
脳卒中や認知症の家族歴がある方
家族や親戚に、脳卒中や認知症の既往歴がある方はとくに注意が必要です。脳卒中のうち「くも膜下出血」は、家族歴(家族の既往歴)がリスク因子であるとされており、親や子ども(一親等以内)が脳動脈瘤を有する場合、自身も脳動脈瘤を有する割合は約4%と報告されています*13。
また、アルツハイマー型認知症の罹患者の15~25%は、家族性(家族のうち3人以上がアルツハイマー型認知症を有する)によるものとされています。とくに、若年性の脳卒中(65歳未満での発症)は、遺伝的要因がより強く影響している可能性が高いとされています*14。
自身はもちろん家族のためにも、40歳を過ぎたら脳ドックを定期的に受け、備えることをおすすめします。
認知症については下記記事もご覧ください。
脳ドックを受けないほうがよいケースもある?
脳ドックでは、MRI装置を用いた検査が行われます。MRI装置は強い磁場を利用した検査のため、受診できないケースもあります。以下にあてはまる場合は、受診前に医師に相談するか、別の検査方法を検討しましょう*1。
- 妊娠中の方、妊娠の可能性がある方
- 心臓ペースメーカーなどの医療機器を体内に入れている方
- 手術後などで、なんらかの金属が体内に残っている方
- 脳動脈瘤の手術(クリッピング術)を受けたことがある方
- 閉所恐怖症の方
- 磁石に反応するインプラントを埋め込んでいる方
とくに体内に金属がある場合、MRIの強力な磁場によって金属が移動したり発熱したりする危険性があるため注意が必要です。また、タトゥーやアートメイクには塗料等に磁性体が含まれていることがあります。これらのように身体から取り外せないものがある方は、検査が可能かどうか、受診前に必ず医療施設へ問い合わせておきましょう。また、MRI検査におけるメイクの注意事項についてまとめた記事もご用意しています。
歯科インプラントについては、一般的によく使われるチタンやチタン合金であればMRI検査を受けて問題ありません。ただし、素材に磁石性の構造物が使われている場合は注意が必要です*15,*16。歯科インプラントを受けている方は、事前に歯科医師やMRIを受ける医療施設に問い合わせておきましょう。
なお、閉所恐怖症の方は、オープン型MRI検査であれば安心して受診できることがあります。
受診してよかった! 脳ドックを受けた人の体験談
脳ドックを受診された方々の体験談をご紹介します。多くの方が、検査の重要性を実感されていました。
ひろこさん(56歳・女性)
父が脳出血で倒れました。私自身も高血圧と脂質異常症と指摘されているので、もし脳内に異変が起きたとしても少しでも早く発見できるよう、毎年脳ドックでMRI/MRA検査を受けています。脳内を調べておくことで、早期発見・早期治療につなげられると思うと安心感があります。…もっと読む
まさしさん(52歳・男性)
同い年の友人が脳梗塞で倒れてリハビリ生活を余儀なくされており、他人事ではないと感じ脳ドックを受けました。検査自体はとくに不安もなく、途中で寝てしまうほどでした。脳の検査は一般的な健康診断には含まれていないので、定期的な脳ドックの必要性を感じています。また3年後に脳ドックを受けるつもりです。…もっと読む
ATさん(44歳・女性)
同僚が若くして亡くなったことをきっかけに、夫婦で人間ドック受診を決意。なかでも、脳はなにかあってからでは遅いので頭部MRI/MRA検査は必ず受けようと決めました。初めての脳ドックで所見がありましたが、すぐに紹介状を用意いただき精密検査を受けられました。幸い大事には至らず、今後もフォローアップしたほうがよい箇所を知ることができ、本当に受けてよかったと感じています。…もっと読む
6raさん(55歳・女性)
母が脳梗塞で他界しました。私も母に似た体質なので、ここ10年ほど毎年脳ドックを受けています。MRIの閉鎖的な空間は毎回苦手ですが、今回受診した施設はアロマサービスがあり、リラックスしながら検査を受けられました。脳の状態は前年から変化なしで一安心。来年また受けようと思います。…もっと読む
KTさん(52歳・男性)
これまでは会社の健康診断と自治体のがん検診を受けていましたが、父や同僚が脳疾患で倒れたことをきっかけに、会社の補助を利用して人間ドック+脳ドックを受け始めました。マーソはさまざまな条件でプランを選べるのが便利です。人間ドックと脳ドックを毎年受けることで数値の経年変化を把握でき、生活習慣の見直しに役立っています。…もっと読む
マーソでは、人間ドックや脳ドックを実際に受けた方の体験談を多数掲載しています。ぜひ参考にしてみてください。
受診者の感想は下記からもご覧いただけます。
https://www.mrso.jp/experience/
マーソではこのほかにも、脳ドックにまつわるさまざまな記事を掲載しています。
https://www.mrso.jp/mikata/category/brain/
参考資料
*1.日本脳ドック学会 脳ドックとは
*2.厚生労働省 令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況 第7表
*3.厚生労働省 2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況 IV 介護の状況
*4.国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」2022年
*5.厚生労働省 健康づくりサポートネット 動脈硬化
*6.日本脳卒中データバンク「脳卒中レジストリを用いた我が国の脳卒中診療実態の把握 報告書 2024年」
*7.九州大学「令和5年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業) 認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究 報告書」
*8.厚生労働省 喫煙の健康影響に関する検討会「喫煙と健康」2016年
*9.厚生労働省 健康づくりサポートネット 喫煙と循環器疾患
*10.厚生労働省 健康日本21企画検討会、健康日本21計画策定検討会「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)について」2000年
*11.厚生労働省 健康づくりサポートネット 肥満と肥満症
*12.Hanson Gabriel Nuamah, et al. The effect of age on the relationship between body mass index and risks of incident stroke subtypes: The JPHC study. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 2024; 33(2)
*13.日本神経治療学会 脳卒中治療ガイドライン2009
*14.GRJ GeneReviewsJapan アルツハイマー病 概説(Alzheimer Disease Overview)
*15.日本口腔インプラント学会 よくあるご質問
*16.日本歯科放射線学会「MRI 検査における over denture の磁性体の取り扱いに関する見解」2021年