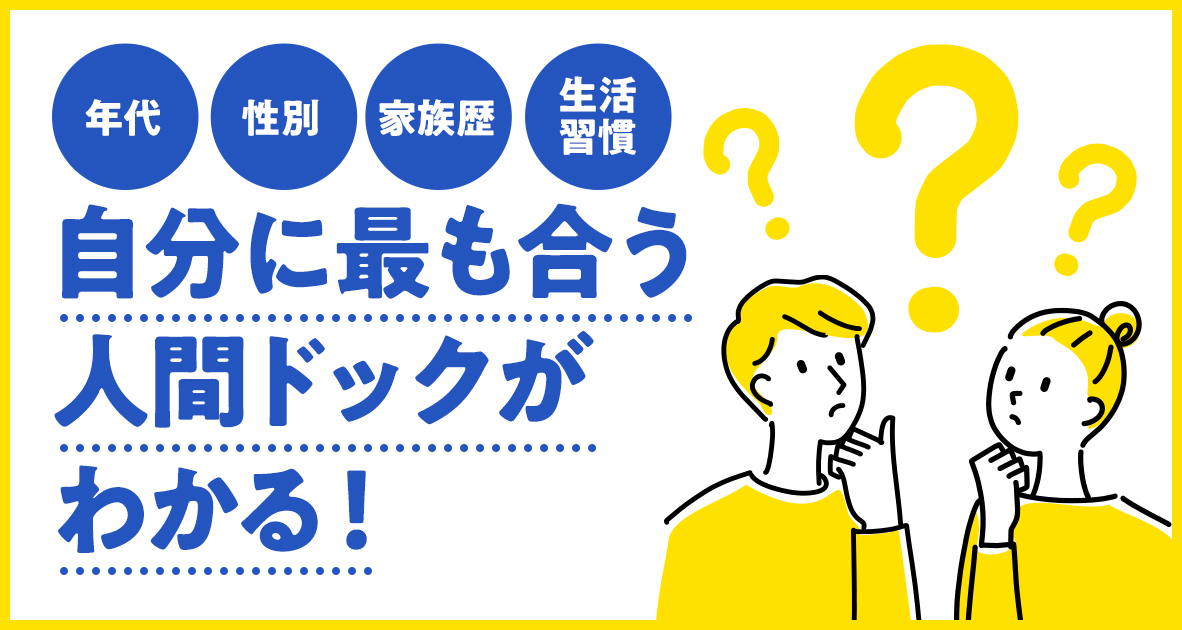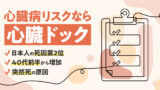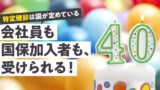人間ドックには多くの種類があります。人間ドックを選ぶポイントは、性別と年齢です。この記事では、自分に最も合う人間ドックを選ぶことができるよう、年齢別・性別それぞれに応じた病気のリスクと検査項目を紹介します。受診する人間ドックにこれらの検査項目が入っているかどうかのチェックリストとしてもお役立てください。
★こんな人に読んでほしい!
・人間ドックの推奨年齢を知りたい方
・自分に合う人間ドックの具体的な検査項目を知りたい方
・年代×性別に応じた病気の発症リスクを知りたい方
★この記事のポイント
・人間ドック受診の推奨年齢は30歳以降、受診頻度は年1回
・人間ドック選びのポイントは「年代×性別」
・検査を選ぶ際は「家族歴」と「生活習慣」も考慮しよう
・年代×性別に応じた病気のリスクとおすすめの検査項目を解説
・人間ドックを選ぶ際は、受けたい検査に対応しているか、機能評価認定施設であるかをチェックしよう
目次
人間ドックはなんのために受ける?
人間ドックの目的は病気の早期発見
人間ドックの目的は、病気の早期発見と将来の発症リスクの把握です。一般的に、病気の発症リスクは年齢を重ねるほど高まります。そこで重要になるのが、いかに早く病気の芽を摘むか、いかに早く病気に気づけるか、ということです。病気の早期発見の有無は、身体的負担はもちろん、治療にかかる時間と費用に明確に直結し、家族や仕事にも影響を及ぼします。場合によっては生死をも分けます。
近年、「人生100年時代」という言葉を耳にする機会が増えました。平均寿命が延び、長くなった人生を健やかに過ごすためには、病気の早期発見とともに「予防医療」と「健康寿命」も着目したいキーワードだと言えます。
予防医療と健康寿命
「予防医療」とは、病気にならないために医療を受ける、という考え方です。長らく、医療とは病気を治すためのものだと考えられてきました。しかし、病気になってから治すのではなく、そもそも病気にならないためのサポートも医療の重要な役割と言えます。人間ドックは、この予防医療に基づいた身体の状態をチェックする機会と言えます。
もうひとつのキーワードである「健康寿命」とは、WHO(世界保健機関)が2000年に提唱した指標です。「寿命」とは一般的に生まれてから死ぬまでの長さのことを指しますが、「健康寿命」はその中でも、健康に過ごしている期間を指します。病院のベッドの上で過ごす時間ではなく、健康に、自分らしく生きる時間を長くすることが、人生の質を高めるために大切です。人間ドックで病気を早期に発見したり、病気の発症リスクを把握したりすることが、健康寿命の延伸につながります。
人間ドックの推奨年齢と受診頻度
人間ドックは何歳から? 30歳を過ぎたら毎年受診しよう
人間ドックは20歳以上で自覚症状のない方であれば誰でも受診できます。おすすめの受診年齢は、ライフステージが変化しやすい30歳以降です。受診頻度は年1回が適当です。
人間ドックは、毎年身体の状態を確認して終了、ではありません。前回の受診結果と比較することで、小さな変化を見つけやすくなります。例えば「前回より肝臓の数値が悪くなったから、お酒を控えよう」といったように、自身の生活習慣を見直すきっかけとなります。こうした経年変化の追跡と定期的な生活習慣の見直しが、病気の予防につながります。
人間ドックの受診適齢期については下記記事もご覧ください。
下記記事では人間ドックを安く受けるヒントを紹介しています。
検査選びで意識したい、「家族歴」と「生活習慣」
人間ドックの検査やプランを選ぶ際に意識したいのが「家族歴」と「生活習慣」です。
家族歴とは、近親者がいつ・どんな病気にかかったかという病歴のことです*1。病気の中には、生まれつき特定の病気になりやすい体質(遺伝要因)により起こるものがあります。代表的なものが、遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)、リンチ症候群(HNPCC)、家族性大腸ポリポーシス(FAP)、家族性高コレステロール血症(FH)、2型糖尿病などです*2-4。また、生活習慣や環境などの類似により、家族などの集団で特定の病気が起こりやすくなる場合もあります。がん家族歴の有無で2グループに分け、双方の罹患リスクを調べた国内研究では、がん家族歴のあるグループは全部位・食道・胃・肝臓・膵臓・肺・子宮・膀胱のがん罹患リスクの上昇がみられたとの報告があります*5。
こうした、特定の病気へのかかりやすさなどを推定するために役立つのが家族歴です。そのため、健康診断や人間ドックの問診票には多くの場合、家族歴の記載欄があります。できれば、自身を中心に3世代(両親・きょうだい・祖父母・おじおば・曽祖父母・大おじ大おば)までの病歴を把握しておけるとよいでしょう*1。
がんと遺伝の関連や家族歴については、下記記事で詳しく解説しています。
女性は人間ドックを何歳から受けたほうがよい?
女性は、乳がんや子宮がんといった女性特有の疾患の早期発見の観点でも、30代から人間ドック(レディースドック)の受診がすすめられます。ただし、性交渉経験がある方は、20代から子宮頸がんの検査を受けましょう。なお、性交渉未経験の方は子宮頸がんの発生リスクは極めて低く、子宮頸がん検診を受ける必要性は示されていないとされています*7。子宮頸がん検診が必要かどうか、事前に医療施設に問い合わせることをおすすめします。
一般的に、がんの発症リスクは年齢とともに高くなりますが、子宮頸がんは20代後半~30代で急増し、40代でピークを迎えます*8。また、乳がんは30代前半から罹患率が増えはじめ、40代後半以降高い値で推移します*8。子宮頸がんも乳がんも、早期に発見し適切な治療を受ければ予後は良好です。万が一病気があったとしてもいち早く気づけるよう、20代、30代のうちから人間ドックやレディースドックなどの受診を検討しましょう。
なお、厚生労働省が指針を定める子宮頸がん検診・乳がん検診の実施年齢および受診間隔は下表のとおりです*9。対象年齢になったら必ず受診しましょう。
| 検査内容 | 対象者 | 受診間隔 | |
|---|---|---|---|
| 子宮頸がん検診 | 問診・視診・子宮頸部細胞診・内診 | 20歳代 | 2年に1回 |
| 問診・視診・子宮頸部細胞診・内診 | 30歳以上 | 2年に1回 | |
| 問診・視診・HPV検査単独法 ※実施体制が整った自治体で選択可能 | 5年に1回 ※罹患リスクが高い方は 1年後に受診 | ||
| 乳がん検診 | 問診・マンモグラフィ ※視診・触診は推奨しない | 40歳以上 | 2年に1回 |
マーソでは子宮頸がん・乳がんに関する記事をたくさん用意しています。下記よりぜひご覧ください。
30代の発症リスクと人間ドック【男女別】
30代男性の発症リスクとおすすめの検査項目
「国民健康・栄養調査結果の概要(2024年)」によれば、30代は、肥満(BMI値25以上)が増加し始める年代です*10。30代男性の34.3%が肥満とされており、運動習慣がある男性の割合が最も少ないのも30〜40代です*10。肥満は動脈硬化を引き起こす要因のひとつであり、動脈硬化が進むと心疾患や脳血管疾患などの将来的な発症リスクが高まります*11。
また、30代男性は、大腸がん罹患率の増加傾向が始まる年代です*8。自覚症状がないうちから、定期的に検査を受けることが早期発見につながります。また、男性のがん罹患数(2021年)の第4位である胃がん*12の検査は、胃X線(バリウム)検査や胃内視鏡(胃カメラ)検査が主流ですが、30代であればヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)を調べる検査も選択肢に入れてもよいでしょう。胃がんの約99%がピロリ菌の感染であることがわかっており、ピロリ菌陽性の場合には胃がんのリスクが5倍以上になるとの国内研究もあります*13。若いうちにピロリ菌の有無を調べる検査を受け、ピロリ菌が見つかったら除菌しておくことが、将来的な胃がんのリスク低減につながります。
加えて、肝臓がんの主因となるB型肝炎・C型肝炎の検査もしておくとよいでしょう。肝炎ウイルスの検査はお住まいの自治体で無料または安価で受けられます。これらを踏まえ、30代男性におすすめの検査項目は次のとおりです。
なお、人間ドックには各学会等が定める基本的な検査のほか、オプション等で受けられる検査があります。本記事では日本人間ドック・予防医療学会が定める「基本検査項目」*14を「基本的な検査」とし、該当外の検査は「オプション等で受けられる検査」とします。
【胃がんの検査】
- 胃X線(バリウム)検査◎
- 胃内視鏡検査
- ピロリ菌検査
- 胃がんリスク検査(ABC検査)
【大腸がんの検査】
- 便潜血検査◎
- 大腸内視鏡(大腸カメラ)検査
【動脈硬化のリスクを調べる検査】
- 血液検査◎
- 眼底検査◎
【肝炎ウイルスの検査】
- B型肝炎ウイルス検査
- C型肝炎ウイルス検査
など
注:◎は日本人間ドック・予防医療学会が定める基本検査項目の「必須項目」に含まれる検査*14。◎以外の検査を受けたい場合は、含まれているプランを選ぶかオプション等で追加することが可能
肝臓がんについては下記で詳しく解説しています。
じゅごんさん(31歳・男性)
父と35歳の先輩の急逝をきっかけに人間ドック+脳ドックを受診しました。お酒をよく飲むので肝臓に問題があるかと思いきや、腎臓の一部石灰化が見つかりました。ビールが影響することもあるらしく、飲酒量に気をつけるようになりました。35歳で亡くなった先輩はくも膜下出血だったので、若くても油断できないと思い、脳ドックは今後も続けていくつもりです。…もっと読む
ころすけさん(33歳・男性)
人間ドックを受けるには若いかもしれませんが、会社の福利厚生で補助が出るので毎年受診しています。前回の胃カメラ検査でピロリ菌が見つかり、胃カメラの重要性を再認識しました。自分は健康だと思っていても、わずかな病気が見つかることもあるので、今後も安心して日々を送るために受診したいと思っています。…もっと読む
30代女性の発症リスクとおすすめの検査項目
30代女性は、女性特有の疾患の検査を強くおすすめします。前述のとおり、子宮頸がんと乳がんは若い年代でも発症するためです。子宮頸がん検診は性交渉経験のある方は20歳から定期的に受診しましょう。
乳がんは日本人女性がもっともかかりやすいがんで、罹患率は30代から急激に高まり、女性のがん死亡数(2024年)は第4位です*8,*12。厚生労働省が定める乳がん検診は40歳以上が対象ですが、早期発見が目的であれば30代から検査を検討しましょう。なお、30代女性は乳腺の密度が高いため、マンモグラフィよりも乳腺超音波(エコー)検査がおすすめです。
また、これまでにピロリ菌や肝炎ウイルスについて調べたことがない方は、これらの検査も検討してみてください。ピロリ菌は胃がんの主因であり、B型・C型肝炎ウイルスは肝臓がんの主因です。いずれも早い段階で感染の有無を確認しておくことが、将来的な発症リスクの低減につながります。30代女性におすすめの検査項目は次のとおりです。
【子宮頸がんの検査】
- 子宮頸部細胞診
- HPV検査
【乳がんの検査】
乳腺超音波(エコー)検査
【胃がんの検査】
- ピロリ菌検査
- 胃がんリスク検査(ABC検査)
【肝炎ウイルスの検査】
- B型肝炎ウイルス検査
- C型肝炎ウイルス検査
など
子宮頸がん・乳がんについては下記記事をご覧ください。
プーさん(34歳・女性)
会社の健康診断では不十分に感じ、婦人科系の検査ができるレディースドックを受けています。自覚症状はありませんが、早期発見が何より大事だと思うからです。私が受診した医療施設は、医師もスタッフも女性のみで、ストレスなくスムーズに受診できました。…もっと読む
ちかさん(37歳・女性)
病気のリスクが増え始める30代後半にさしかかり、とくに婦人科系を中心に詳細な検査をしたいと思いレディースドックを受けました。すると、意外にも胸部CT検査で肺に白い影が見つかり再検査に。普段健康だと病気になることなど考えないと思いますが、思わぬ病気の種が見つかるものだと身をもって感じました。…もっと読む
40代の発症リスクと人間ドック【男女別】
40代男性の発症リスクとおすすめの人間ドック
40代男性の肥満割合は35.8%で、30代より若干上がります*10。生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合は40〜60代で高く、喫煙習慣がある人の割合は40代が最も高くなっています*10。心疾患や脳血管疾患の発症リスクに一層の注意が必要です。
部位別に見たがんの罹患数は、大腸と肺、腎・尿路の増加が顕著となります*15。また、50代以降に増える胃がんと膵臓がん、前立腺がんへの備えとして、これらの検査も40代のうちから受けましょう。肝臓がんの原因となる脂肪肝にも要注意です。とくに肥満を指摘されている方は、飲酒量にかかわらず肝臓の検査も加えるとよいでしょう。40代男性には、30代男性の項で挙げた検査に加え、下記の検査をおすすめします。
【肺がんの検査】
- 胸部X線(レントゲン)検査◎
- 胸部CT検査
- 喀痰検査(喀痰細胞診)
- 呼吸機能検査◎
【膵臓がんの検査】
- 腹部超音波(エコー)検査◎
- 上腹部CT検査(造影剤あり)
- MRCP
【肝臓がんの検査】
- 血液検査◎
- 腹部超音波(エコー)検査◎
【腎・尿路がんの検査】
- 尿検査◎
- 腹部超音波(エコー)検査◎
【前立腺がんの検査】
腫瘍マーカーPSA検査(血液検査)
など
注:◎は日本人間ドック・予防医療学会が定める基本検査項目の「必須項目」に含まれる検査*14。◎以外の検査を受けたい場合は、含まれているプランを選ぶかオプション等で追加することが可能
前立腺がん検査の詳細は下記でご覧いただけます。
福丸さん(44歳・男性)
会社の福利厚生で人間ドックを受けています。親戚に胃がんで亡くなった方がおり、それをきっかけにバリウム検査から胃カメラ検査に変更しました。初回は経口・鎮静剤なしで苦しい思いをしたので、次から鎮静剤ありにしたら、まったく苦痛なく検査できるようになりました。健康管理で最も重要なことは早く異変に気づくことだと思うので、人間ドックで自分の弱点を知るだけでも大きな一歩になります。…もっと読む
しょうじさん(44歳・男性)
せっかく検査するなら精度の高いものを受けたいと思い、会社の補助を利用して人間ドック・脳ドックを受けています。とくに脳血管の詰まりなどは直接確認することができないため、定期的に検査したいです。脳の検査は高額なイメージがあるかもしれませんが、検査精度の高さや撮影画像が記録として残る点で、受診する価値があると思っています。…もっと読む
40代女性の発症リスクとおすすめの検査項目
40代女性は、引き続き子宮頸がんと乳がんの検査を受けましょう。40代の乳がんの検査は乳腺超音波(エコー)検査よりマンモグラフィが適しているとされています。ただし、高濃度乳房(デンスブレスト)を指摘されたことがある方は、乳腺エコー検査のほうが向いている場合もあります。検査方法に迷う方は、医療施設に問い合わせてみましょう。
女性は40代以降、子宮体がんと卵巣がんの罹患数が増加するため、婦人科系疾患を網羅的に調べることをおすすめします*15。乳がんの検査、子宮頸がんや子宮体がんの検査のほか、経腟超音波(エコー)検査が含まれる婦人科検診やレディースドックなどを検討しましょう。経腟エコー検査では、卵巣がんやその他子宮周辺の疾患(子宮内膜症、子宮筋腫など)を調べることができます。女性特有の疾患以外では、胃がん・大腸がん・肺がんの罹患数も増加傾向となります。また、女性も50歳以降、膵臓がんによる死亡数が増加します*8。これらの早期発見の観点から、40代のうちに各部位の検査を受けましょう。
加えて、40〜50代にかけては、ホルモンバランスが変化する時期でもあります。内臓脂肪や、骨密度の変化にも留意しておきましょう。40代女性には、30代女性の項で挙げた検査に加え、下記の検査をおすすめします。
【乳がんの検査】
マンモグラフィ
【子宮体がんの検査】
子宮体部細胞診
【卵巣がんやその他子宮周辺の疾患を調べる検査】
経腟超音波(エコー)検査
【胃がんの検査】
- 胃X線(バリウム)検査◎
- 胃内視鏡(胃カメラ)検査
【肺の検査】
- 胸部X線(レントゲン)検査◎
- 肺CT検査
【大腸がんの検査】
- 便潜血検査◎
- 大腸内視鏡(大腸カメラ)検査
【膵臓の検査】
腹部超音波(エコー)検査◎
【その他】
骨密度検査
など
注:◎は日本人間ドック・予防医療学会が定める基本検査項目の「必須項目」に含まれる検査*14。◎以外の検査を受けたい場合は、含まれているプランを選ぶかオプション等で追加することが可能
40代以上の女性に向けて、骨密度検査の記事を用意しています。ぜひご覧ください。
みちるさん(40歳・女性)
毎年人間ドックを受けていましたが、産後に受診しなかった年がありました。その翌年に上司のすすめで人間ドックを受診したところ、子宮頸がんの前がん状態が発覚。早期に見つけられたことで治療できました。あのとき子宮頸がん検診を受けていなかったら…と思うと、受診をすすめてくれた上司には感謝の気持ちでいっぱいです。…もっと読む
みるくさん(44歳・女性)
生命保険会社の特典を利用して人間ドックを受けています。それまで、胃がん・子宮がん・乳がん健診はそれぞれ別の病院で受けていて効率が悪かったですが、人間ドックはすべての検査が1日で終わるので私には合っています。私は生命保険の特典に加え、自治体の補助も活用し、半額程度で人間ドックを受診できています。…もっと読む
50代の発症リスクと人間ドック【男女別】
50代男性の発症リスクとおすすめの検査項目
「令和6年(2024)人口動態統計」によれば、50代男性の死因順位は、1位:悪性新生物、2位:心疾患、3位:自殺(50〜54歳)・脳血管疾患(55〜59歳)です*16。また、同じ疾患による死亡数を50代男女で比較すると、心疾患による50代男性の死亡数は50代女性の死亡数の4倍以上、脳血管疾患による死亡数は2倍以上です。
心疾患の代表例は心臓病(狭心症、心筋梗塞など)で、とくに急性の心筋梗塞は突然死の原因にもなっています。脳血管疾患の代表例は脳卒中(脳梗塞、くも膜下出血、脳出血など)で、死に至らない場合であってもなんらかの後遺症を引き起こすことが多く、「国民生活基礎調査(2022年)」によれば、介護が必要になったおもな原因の第2位になっています*17。
心疾患や脳血管疾患の要因には動脈硬化が深く関わっており、高血圧症や脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病あるいはそれらの兆候の把握のために、定期的なチェックが欠かせません。健康診断や基本的な人間ドックに含まれている心電図検査では、初期の心臓病は見落としやすいです。基本的な人間ドック以外に、心臓ドックや脳ドックも検討してください。また、一度にほぼ全身のがんのスクリーニングをする検査を選択肢に入れてもよいでしょう。50代男性には、40代男性の項で挙げた検査に加え、下記の検査をおすすめします。
【心臓の検査】
- 冠動脈CT検査
- 心臓MRI検査
- 心臓超音波(エコー)検査
- 運動負荷心電図検査
【脳の検査】
- 頭部MRI/MRA検査
- 頸動脈超音波(エコー)検査
【全身のがん検査】
- PET検査
- 全身DWIBS(ドゥイブス)
など
心臓ドック・脳ドックの詳細は下記記事をご覧ください。
まさしさん(52歳・男性)
同い年の友人が脳梗塞で倒れ、リハビリ生活を送っています。他人事ではないと思い、会社の健康診断にはない脳の検査もできる人間ドックの受診を決めました。病気になることは、自分だけでなく家族への影響も大きいと考えます。将来後悔しないためにも、定期的な受診を続けたいです。…もっと読む
とみさん(50歳・男性)
会社の健康診断の便潜血検査で精密検査が必要となったことをきっかけに、人間ドックで身体をきちんと調べようと思いました。食道や肝臓に所見があったほか、オプションのMRCPでは胆嚢腺筋症が見つかりました。悪化する前に見つかってよかったです。…もっと読む
50代女性の発症リスクとおすすめの検査項目
「令和6年(2024)人口動態統計)」によれば、50代女性の死因1位は悪性新生物(がん)で、がんの種類別でみると乳がん、大腸がん、子宮がん(子宮頸がん+子宮体がん)、卵巣がんが多くを占めています*16,*18。
50代女性は、40代と比較し心疾患や脳血管疾患のリスクも高まります*16。これは、閉経による影響も考えられています。閉経によるエストロゲンの減少は骨粗鬆症(骨粗しょう症)のほか、高血圧症や脂質異常症などにも影響するとされています*19,*20。これらは動脈硬化を助長し、ひいては心疾患や脳血管疾患を招くこともあるため、高血圧や肥満などを指摘されたことがある方は、心臓や脳のより詳細な検査を検討しましょう。50代女性には、40代女性の項で挙げた検査に加え、下記の検査をおすすめします。
【心臓の検査】
- 冠動脈CT検査
- 心臓MRI検査
- 心臓超音波(エコー)検査
- 運動負荷心電図検査
【脳の検査】
- 頭部MRI/MRA検査
- 頸動脈超音波(エコー)検査
【全身のがん検査】
- PET検査
- 全身DWIBS(ドゥイブス)
など
膵臓がんについては下記で詳しく解説しています。
pomさん(56歳・女性)
これまで会社の健康診断で十分と思っていましたが、なんとなく思いたって人間ドックを受けてみました。結果、胸部CT検査で肺の腫瘍が見つかり手術しました。喫煙もしないので本当に驚きましたが、会社の健康診断では見つけにくい部分にあったそうで、人間ドックの重要性を痛感しました。…もっと読む
simaenagaさん(51歳・女性)
両親ともがんのため、がん家系かもしれないと思いながらも受診機会がありませんでした。そんなとき、家族が申し込んでくれたことで人間ドックを受けました。結果は、便潜血検査や脂質異常症、クレアチニンで異常を指摘されました。どれも自覚がなかったので、知らないまま過ごしていたら…と怖くなりました。…もっと読む
60代の発症リスクと人間ドック【男女別】
60代男性の発症リスクとおすすめの検査項目
60代男性の死因順位は、1位:悪性新生物、2位:心疾患、3位:脳血管疾患です*16。50代男性と比較して悪性新生物(がん)による死亡数が急増し、とくに肺がんによる死亡数増加が他の年代の男性に比べて顕著です*18。また、あらゆるがんの罹患数が右肩上がりに増加します。
厚生労働省の「国民健康・栄養調査報告(2024年)」によると、60代男性の33.6%が肥満であり、糖尿病が強く疑われる人は20.5%です*10。60代は、30代・40代での生活習慣が表面化する年代ととらえることができます。30代から定期的に身体の状態を把握し経年変化を追い、生活習慣を意識しながら過ごすことが、60代の健康、ひいては健康寿命に影響を及ぼすと言えそうです。60代男性は、50代男性の項で挙げた検査がおすすめです。また、基本的な脳ドックに認知症の兆候を把握する検査の追加も検討してはいかがでしょう。下記は脳ドックのオプション等で受診できる検査の例です。なお、これらは認知症の兆候などを調べる検査であり、脳ドックでは認知症の診断は行われません。
【脳の検査】
- VSRAD®(ブイエスラド®)
- MCIスクリーニング検査
- 簡易脳機能検査
など
VSRAD®の詳細は以下でご覧いただけます。
ぎすけさん(64歳・男性)
会社の福利厚生で毎年人間ドックを受けています。以前、ピロリ菌除菌を行っていますが、人間ドックで医師も驚くほど早期の胃がんが見つかり、切除できたことがあります。早期に発見してもらえたことに感謝しかありません。…もっと読む
トシ君さん(68歳・男性)
65歳を過ぎ、飲酒量も多いため、一度人間ドックで詳しく検査したく受診しました。脳ドックは年齢的にも必要性を感じ、今後も定期的に受けるつもりです。また、前回の大腸カメラ検査ではポリープを複数個切除しています。放置していたら悪性になっていた可能性もあるため、大腸カメラも定期的に受診したいです。…もっと読む
60代女性の発症リスクとおすすめの検査項目
60代女性の死因順位は、1位が悪性新生物、2位が心疾患、3位が脳血管疾患です*16。がんによる死因の上位は乳がん、大腸がん、肺がんのほか、膵臓がんも顕著に増加しています*18。
60代女性は、生活習慣病のリスクも高まります。厚生労働省「国民健康・栄養調査報告(2024年)」によると、60代女性の20.6%が肥満で、糖尿病が強く疑われる人の割合は11.2%です*10。50代から引き続き、定期的な検査で動脈硬化のリスクを把握しておきましょう。また、認知症が不安な方は、基本的な脳ドックに認知症の兆候を把握する検査の追加も検討してもよいでしょう。脳ドックでは認知症の診断は行われませんが、認知症の兆候を調べることは可能です。50代女性の項で挙げた検査に加え、下記の検査をおすすめします。
【脳の検査】
- VSRAD®(ブイエスラド®)
- MCIスクリーニング検査
- 簡易脳機能検査
など
脳ドックにおける認知症の検査については下記記事で詳しく解説しています。
やまもとさん(61歳・女性)
閉経後、高血圧や体重増加が気になり人間ドックを受けました。会社の健康診断にはない検査を受けたくて、胃カメラ検査と骨密度検査が含まれたプランにしました。結果は意外と悪くなくホッとしたと同時に、次回は脳ドックや腫瘍マーカー検査など、受けたことのない検査をやってみようという健康意識が芽生えました。…もっと読む
お母さんさん(61歳・女性)
胸やけなどが気になっていたところ、子どもが人間ドックギフト券を贈ってくれ、初受診に至りました。胃カメラ検査は鎮静剤を使用し、眠っている間に苦痛なく終えられました。胃の壁に異常があり治療していますが、がんなどではなかったので安心しています。最近もの忘れが多いので、脳の検査も気になっています。…もっと読む
何歳まで人間ドックを受診したほうがいい?
人間ドックに年齢制限はある?
人間ドックは20歳以上であれば誰でも受診でき、何歳までという年齢の上限は設けられていません。なお、会社員が年に1回受ける「定期健康診断」は、年齢を問わずその企業に常時雇用されている人が対象で、国が定める「特定健診」の対象は40〜74歳です。75歳以上の方は居住する自治体が実施する「後期高齢者健康診査」(名称は異なる場合がある)で特定健診と同様の検査を受けられます。より詳細な検査を希望する場合は人間ドックなどを検討してもよいでしょう。
健康診断と特定健診、人間ドックの違いを知りたい方は、下記もご覧ください。
高齢者にも人間ドックは必要?
高齢の方でも、これまで大きな病気もなく過ごしてこられた方、持病以外の検査を受けることがあまりない方などは、人間ドックが身体の状態をより詳しく把握するよい機会になり、ひいては健康寿命の延伸につながると言えます。自治体によっては、75歳以上の方に人間ドックの補助・助成を行っていることがありますので、お住まいの自治体に問い合わせてみてください。
なお、高齢の方の場合は、基準値等が若年期とは異なる場合があります*21。こうした事情への理解度が高く、高齢の方に適した検査や対応が行える医療施設を選ぶとよいでしょう。
「人間ドックは受けないほうがいい」は本当?
「人間ドックは受けないほうがいい」「健康診断を受けているから人間ドックは必要ない」といった話を見聞きすることがあるかもしれません。医療において、この検査をすれば100%病気が見つかる、と言い切れるものはなく、検査によってはごく稀に合併症が起こったり、治療の必要性が低い病気が見つかったりするなどの不利益をともなう場合もあります。
他方で理解しておきたいのが、がんなど命に関わる病気の多くは、初期には自覚症状がほとんどないということです。自分では気づけないからこそ、病気があったとしても早期に見つける手段として人間ドックがあります。人間ドックは一般的な健康診断よりも検査項目数が多く、精密な検査を行うことも多いため、一般的な健康診断では気づきにくい病気の兆候を発見できる可能性が高くなります。
こうした人間ドックを受けることのメリット・デメリットを理解し、自身が納得したうえで受診できることが望ましいと言えます。
人間ドック施設の選び方のコツ
優先順位の3大ポイント! 受けたい検査・コスト・アクセス
人間ドックの医療施設選びに迷ったら、次の3つのポイントを参考にしてください。
希望する検査を実施している
自身の年齢と性別、家族歴、生活習慣などを勘案し、受けたい検査項目を決めたうえで医療施設を選びましょう。希望の検査があらかじめプランに組み込まれているか、あるいはオプションなどで追加するのかも確認しておきましょう。
費用が予算と合っている
人間ドックは自由診療のため、価格や内容は医療施設が自由に設定します。検査項目は同じでも医療施設によって価格が異なります。希望の条件に当てはまるプランをいくつか見比べたうえで、受診先を検討してもよいでしょう。
自宅や勤務先からアクセスしやすい
経年によるデータを蓄積する意味では、人間ドックはできれば毎年同じ施設で受診することが望ましいです。定期的な受診を想定すると、自宅からのアクセス、終了後の勤務先へのアクセスなども考慮するとよいでしょう。
マーソでは、さまざまな条件から医療施設を検索できます。
「機能評価認定施設」であるかどうかをチェックしよう
医療施設選びの指針となるのが「機能評価認定施設」であるかどうかです。
機能評価認定施設とは、日本人間ドック・予防医療学会が定める評価基準をクリアした医療施設です*22。審査項目には、「運営方針、組織の管理体制が確立しているか」や「検査の業務マニュアルは作成されているか」、「感染対策などの危機管理は徹底されているか」といった施設側の安全面に関する基準から、「受診者が快適に受診できるように配慮しているか」や「受診者のプライバシーに配慮しているか」といった受診者側に関する基準まで、多角的な評価基準があります。評価・認定審査は5年ごとに行われているため、品質を保ち続ける努力をしている施設を探すのに役立ちます。
機能評価認定施設一覧はこちら(外部サイト)
参考資料
*1.日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構 遺伝性乳がん卵巣がんを知ろう! みんなのためのガイドブック2022年版「Q13.遺伝カウンセリングで家族の病歴を尋ねられました。どこまで伝える必要がありますか?」
*2.日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍とは
*3.日本動脈硬化学会 家族性高コレステロール血症(FH)とは?
*4.日本内分泌学会 2型糖尿病
*5.国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト 多目的コホート研究「がん家族歴と、その後のがん罹患リスクとの関連について」
*6.厚生労働省 健康づくりサポートネット 生活習慣病とは?
*7.国立がん研究センター がん情報サービス 子宮頸がん検診について
*8.国立がん研究センター がん情報サービス がん統計 がん種別統計情報
*9.厚生労働省 がん検診
*10.厚生労働省 「令和6年(2024) 国民健康・栄養調査結果の概要」
*11.日本動脈硬化学会 動脈硬化性疾患とは?
*12.国立がん研究センター がん情報サービス がん統計 最新がん統計
*13.国立がん研究センター 予防関連プロジェクト 多目的コホート研究「ヘリコバクター・ピロリ菌感染と胃がん罹患との関係:CagAおよびペプシノーゲンとの組み合わせによるリスク」
*14.日本人間ドック・予防医療学会 基本検査項目/判定区分
*15.厚生労働省「令和5年(2023)全国がん登録 罹患数・率 報告」
*16.厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」第7表
*17.厚生労働省「2022年(令和4)国民生活基礎調査の概況」IV 介護の状況
*18.がん研究振興財団「がんの統計2024」
*19.日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」
*20.日本女性心身医学会 女性の病気について
*21.日本人間ドック・予防医療学会「高齢人間ドック受診者 指導の手引き 2020年3月版」
*22.日本人間ドック・予防医療学会 機能評価認定施設一覧